近年の分子分類学的手法の発展により、タンパク質の類似や遺伝子の塩基配列情報からより確かな系統関係の構築が可能になった。針葉樹類の分類に関しては、早くから免疫距離に基ずくヒノキ科とコウヤマキ科、あるいはマツ科の系統構築が行われ、さらに近年葉緑体DNA上のrbcL遺伝子の塩基配列データの蓄積が進められている。このように現生分類群間の系統関係が明らかになることにより、ある分類群がいつ、どこで、どのような形態進化の過程を経て生じたかを明らかにすることが不可欠になってきた。そのためのよりどころとして化石情報の重要性が高まってきている。しかし化石の産出は限られており、すべての分類群において化石と現生双方の情報を総合した研究が可能であると言うわけではない。北海道の白亜紀浅海性堆積層からは、多くの植物化石が産出することが知られており、しかもそれらは内部構造が保存され、形態的情報量に富んだ石化化石である。ことに針葉樹類の球果はその量と多様さにおいて世界に比類ないものである。一方現生針葉樹類については従来の形態学的研究の蓄積に加えて近年分子分類学的研究も大きく進み、属や科のレベルの系統関係が比較的はっきりしてきた。従って針葉樹類は化石と現生植物をあわせた系統関係構築のモデルケースとして最適である。本研究は、北海道白亜紀から多産する針葉樹の雌性球果化石を記載する一方で、それらの情報をもとに現在のいくつかの科に関しての進化史を明らかにすることを目的とする。 針葉樹球果化石は1900年代の諸外国における情報の集積に比べ、日本における研究は遅れており、Stopes and Fujii(1910)の記載したCunninghamiostrobus yubariensis以降研究が途絶えていたが、1990年以降研究が再開され数例の報告がなされつつある(表1)。本研究では新たにナンヨウスギ科、ヒノキ科、マツ科、及びコウヤマキ科の球果化石計8種を記載した(表1)。その中にはナンヨウスギ科の新種のように、その発見自体が節レベルの絶滅群の発見であるような場合もあり、化石でなければ復元不能な古植物研究の伝統的側面をみせるものもある。他方ヒノキ科やマツ科などの研究成果は現生種の最新の系統分類学的成果と化石情報を融合させた系統構築の新しい方向性を示すものである。以下にその概要を示す。 ナンヨウスギ科:現在南半球に分布が限られるナンヨウスギ科は、中生代には北半球にも優先種として森林を形成していた。北海道からも様々な器官が記載されている。本研究では北海道の白亜系から従来知られていたシュート化石Yezonia vulgarisとナンヨウスギ属の球果Araucaria nihongiiが同一の植物であることを明らかにし、植物体全体を復元した。さらに現生種との比較形態に基づき復元されたAraucaria vulgaris(新組み合わせ、図2)をもとに、新節Yezoniaを提唱した。従来ジュラ紀以前からは現生4節のうちEutacta節とBunya節が知られ、ナンヨウスギ属のなかで原始的な節であると考えられてきた。しかしジュラ紀以前のEutacta型の球果はYezonia節である可能性がある。 ヒノキ科(広義):広義のヒノキ科に関して最近のデータは、従来のスギ科が狭義のヒノキ科を内部に含む側系統群であるということを示しており、狭義のヒノキ科の分化過程や、広義のヒノキ科内の分類群の分岐年代が議論されている。本研究ではすでに北海道から知られていたYezosequoia,Parataiwaniaに加え、Haborosequoia,Archicupressus,Yubaristrobusの3属を記載した(図3)。このうちArchicupressusとYubaristrobusは狭義のヒノキ科と形態的類似がみられ、世界的に類をみない石化化石である。これらの記載を基にWagner節約法により球果の形質による系統解析を行った(図4)。この分岐図においてヒノキ科は先細りの果鱗複合体を持つグループと先太りの果鱗複合体を持つグループの大きく2つに分かれた。また狭義のヒノキ科における形質の系統発生の順序が示された(図5)。各分類群の出現時期を考えると、ヒノキ科の二大グループの分岐はジュラ紀末から白亜紀の始めと考えられる。さらに各グループが白亜紀後期に急速に多様化したことがわかる。 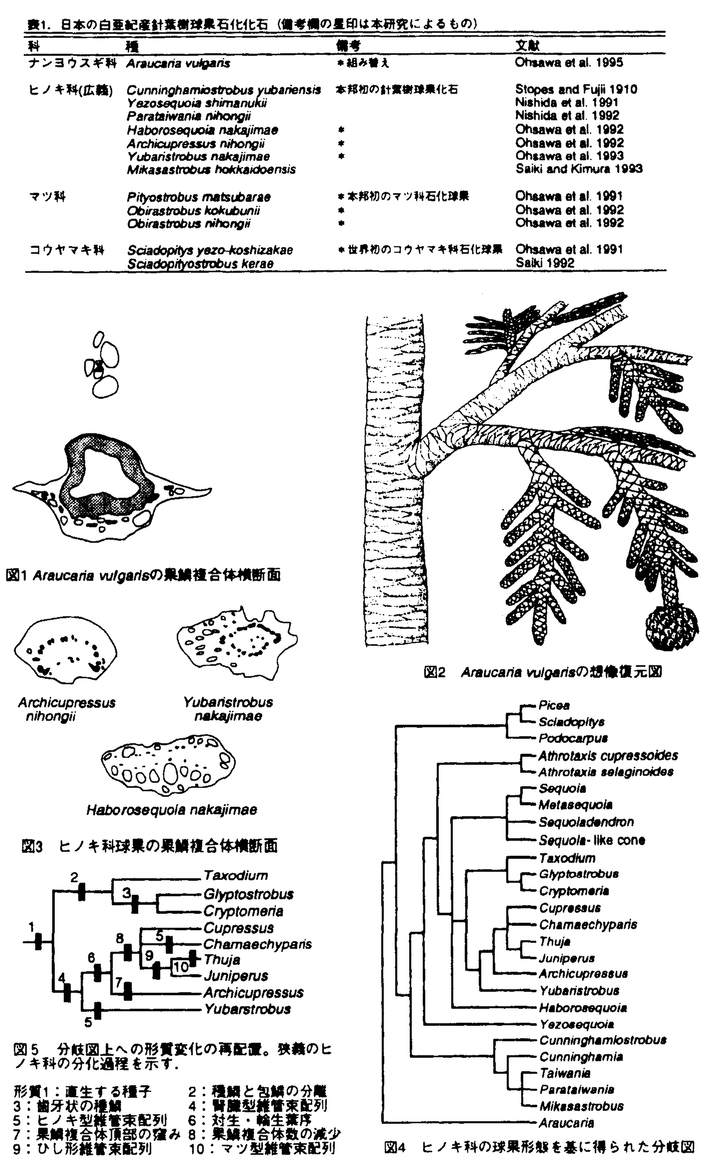 図表表1.日本の白亜紀産針葉樹球果石化化石(備考欄の星印は本研究によるもの) / 図1 Araucaria vulgaris果鱗複合体横断面 / 図2 Araucaria vulgarisの想像復元図 / 図3 ヒノキ科球果の果鱗複合体横断面 / 図4 ヒノキ科の球果形態を基に得られた分岐図 / 図5 分岐図上への形質変化の再配置。狭義のヒノキ科の分化過程を示す. 図表表1.日本の白亜紀産針葉樹球果石化化石(備考欄の星印は本研究によるもの) / 図1 Araucaria vulgaris果鱗複合体横断面 / 図2 Araucaria vulgarisの想像復元図 / 図3 ヒノキ科球果の果鱗複合体横断面 / 図4 ヒノキ科の球果形態を基に得られた分岐図 / 図5 分岐図上への形質変化の再配置。狭義のヒノキ科の分化過程を示す. マツ科:マツ科は従来栄養器官の形態で分類されていたが、最近の分岐分析、免疫距離、DNA塩基配列などのデータでは全く別の分類が支持されている。マツ科の球果化石は多くの場合現生属に当てはめることはできず、器官属のPityostrobusかPseudoar aucariaに含められているが、Pseudoaraucariaが一定の形質によって定義されているものであるのに対して、Pityostrobusはその他のマツ科の球果化石をすべて含む非常に雑多なものの集まりであり、いずれ分類学的再検討がなされるべきものである。本研究ではPityostrobus1種に加え、近縁な2種が見つかったものに関してはPityostrobusを適用せずに明確な自然分類群を見いだし、Pseudoaraucaria以来の新属としてObirastrobusを新設した(図6)。これらのマツ科の化石分類群は類縁がはっきりしていないため、科の進化史に対して十分に有効な情報を与えているとはいえない。 そこでObirastrobus、Pseudoaraucaria及びPityostrobusの各種の類縁を明らかにし、科内での形態進化の過程、各分類群の分岐時期などを推定するために、球果の形態に基ずく系統解析を行った。その際PAUPのbackbone constreintsのオプション使い、現生資料に基ずく分岐を基準とし、その分岐関係を壊さない範囲で化石分類群がどの位置に配置されるかを解析した(図7)。その結果、ObirastrobusとPseudoaraucariaはそれぞれ単系統となり、独立の属とすることが支持された。Obirastrobusは現生属との関連が特に見られないが、Pseudoaraucariaはカラマツ亜科と単系統群を形成する。Pityostrobusは、1:モミ亜科と単系統になるもの、2:カラマツ亜科と単系統になるもの、3:マツ亜科と単系統になるもの、4:現生属と特に関係が見られないもの、の少なくとも4群にに分けられる(表2)。本研究で記載されたPityostrobus matsubaraeは科の基部に位置することが示された。マツ属には特有な4形質が知られるが、化石分類群を扱うことにより、その出現の順番が明らかにされた(図7)。  図表図6 マツ科球果化石の種鱗基部の樹脂道の様子を示す模式図 / 図7.マツ科球果化石の形態形質に基ずく分岐図(Strict consensus tree).バーはマツ属固有の形質を再配置させたもの.黒のバーは形質の獲得,綱掛けのバーは形質の消失を表す. / 表2. Pityostrobusのグループ分け 図表図6 マツ科球果化石の種鱗基部の樹脂道の様子を示す模式図 / 図7.マツ科球果化石の形態形質に基ずく分岐図(Strict consensus tree).バーはマツ属固有の形質を再配置させたもの.黒のバーは形質の獲得,綱掛けのバーは形質の消失を表す. / 表2. Pityostrobusのグループ分け 分岐図上の各分類群の時間分布をみると、トウヒ亜科を除けばそれぞれの単系統群が白亜紀最下部の種を含んでいる。このことからマツ科のすべての単系統群はジュラ紀末以前に分かれたことが示唆された。これらの各単系統群の分化の過程を知るために、ジュラ紀の材料を解剖学的に調べることの必要性を強調した。 コウヤマキ科:日本固有の属であるコウヤマキ属は長年ヒノキ科の一員とされてきたが、免疫距離やrbcLの塩基配列からはヒノキ科からかなり遠い関係にあることが示されており、最近では早田の提唱したコウヤマキ科が受け入れられている。本研究では北海道の白亜紀から世界で初めてコウヤマキ科の石化球果化石を記載した。この球果は現生種とほぼ同じ特徴を持っており、小倉(1932)による葉の石化化石とあわせて現生種と同じような特徴を持った植物が白亜紀の後期には存在していたことを証明した。 本研究によりナンヨウスギ属の1新節1種、ヒノキ科の3新属3種、マツ科のPityostrobus属と1新属の3種、コウヤマキ属の1新種が記載された。これらは日本における針葉樹球果化石の情報を飛躍的に増やしたばかりでなく、ナンヨウスギ属の特殊な分類群や、狭義のヒノキ科と類縁のある球果、マツ科の石化球果の新属、コウヤマキ科の球果など、世界的に見ても分類学上貴重な発見も含まれる。さらにマツ科とヒノキ科で示されたように、これらの化石情報を系統解析に加えることにより、形態進化の過程や分岐の時期などを従来よりはるかに客観的に示すことができた。 |