構造物を支える深い大型基礎の代表的なものとして、ニューマチックケーソン基礎があるが、周辺地盤を緩めるほか、潜函室内という劣悪な環境下での作業が必要など労働力の確保という観点からも代替工法の開発が望まれていた。 連壁剛体基礎は、従来、仮設物に使われることの多かった地下連続壁を、平面形状が口・日・田のような形状に掘削し、コンクリートを閉合打設して築造するものである。剛性が高く、支持力も大きいこと、全ての作業が地上で行えることなど、ニューマチックケーソン基礎に変わり得るものであるが、荷重を受けたときの連壁剛体基礎の挙動の算定方法や分割施工された場合の継手の挙動・耐力など不明確な点があった。本論文は、連壁剛体基礎の設計に当たって必要なこれらのことを明らかにし、算定方法を提案したものである。 (1)連壁剛体基礎の計算法の基になっているケーソン基礎の計算法に付いて研究し、従来のケーソンの計算で期待している地盤の強さに比べて実際の周辺地盤はケーソンの施工によって大きく緩むことを調査研究した。その結果、ケーソン周辺地盤の緩みは、緩み範囲の中においてケーソンの側壁に近づくに連れて指数関数的に緩むこと、側壁直近の地盤のN値は原地盤のN値が大きくなっても余り大きくならない(すなわち、原地盤のN値が大きいほど緩みの程度が大きい)こと等が判明した。そしてこの研究結果を基に、(1)式に示す標準緩み曲線を作成した。すなわち、  ここに、Ex:側壁からの離れxの位置の緩んだ状態での変形係数(kgf/cm2) E0:原地盤の変形係数(kgf/cm2) x:側壁からの離れ(cm) l:緩み範囲(一般部;砂質度150cm,粘性度100cm 刃口部;砂質度、粘性土とも一般部の2/3とする) n:一般部=1,刃口部=0.5 N0:原地盤のN値 Ns:標準N値(=25),m:係数(=2) これを基に、(2)式により等価変形係数Eeqを求め、ケーソンの水平載荷試験結果と照合し、Eeqの妥当性を検証した。また、無次元化した緩み係数 (=Eeq/Eo)を求める図表を作成した。 (=Eeq/Eo)を求める図表を作成した。  ここに、P:荷重 Ax:側壁からの離れxの位置の荷重分散を考慮した荷重分担面積 R:影響範囲(cm) ケーソン前面の幅をB(cm)、荷重分散角を として、R=B/(0.5B1/4-2tan として、R=B/(0.5B1/4-2tan ) ) (2)地下連続壁は、泥水圧で溝壁を抑えながら掘削するので周辺地盤の緩みが小さく、またコンクリートを直接溝壁の中に打ち込むので、壁体と地盤が密着し、かなりの周面摩擦力を期待できる。また、大きさのほぼ同一なケーソン基礎と連壁剛体基礎を互いに引張り合う水平載荷試験を行ったところ、連壁剛体基礎の変位はケーソン基礎の変位の約1/5であった。これらのことから荷重を受けたときの基礎を支える地盤バネとして、ケーソン基礎では側壁前面の水平方向バネk1(図1参照,以下同じ),底面の鉛直方向バネk7,せん断バネk8のみを考慮しているのに対して、連壁剛体基礎では図1ならびに表1に示すように8種類のバネを考慮した(以後「連壁基礎法」という)。ケーソン基礎では周辺地盤が緩んでしまうため地盤とはせいぜい主働土圧程度でしか押し合っていないとの考え方から前面側のk1および両側面に働く摩擦抵抗として合計してk1の20%しか考慮できなかったのに対して、連壁剛体基礎では地盤と静止土圧状態で押し合っていると仮定しk1は後面側にも有効であると考え、また、側面に作用するせん断バネk5はk1の60%程度の大きさがあると考えた。さらに、連壁剛体基礎では前後面の鉛直方向せん断バネk2も有効に効くと考えた。これらのせん断バネや連壁剛体基礎内面のバネは、平面形状が正方形で地下連続壁の長さが平面寸法のほぼ2倍のものについて有限要素解析法によりk1との比を求めたものである。また、これらのバネと変位から算出される地盤反力の最大値(または最小値)は、受働土圧・主働土圧・周面摩擦力等である。周面摩擦力については地下連続壁と施工方法が同じである場所打ち杭の鉛直載荷試験結果を収集しそれらを整理して求めた。飯坂街道Bv.,王子南部B1.における水平載荷試験結果と連壁基礎法による計算結果とを照合し、連壁基礎法の妥当性を検証した。 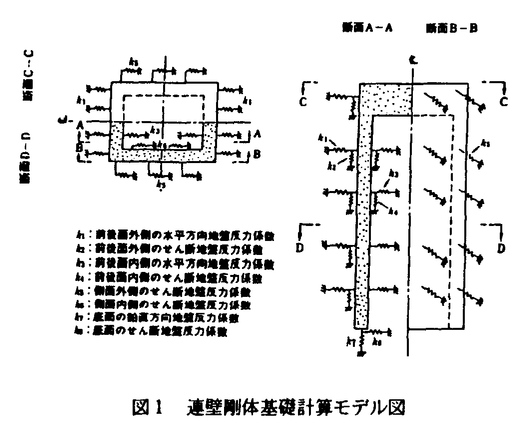 図1 連壁剛体基礎計算モデル図 図1 連壁剛体基礎計算モデル図 表1 連壁剛体基礎地盤反力係数の一覧表 表1 連壁剛体基礎地盤反力係数の一覧表 (3)連壁剛体基礎の水平主鉄筋の重ね継手は、施工上の制約から梁の高さ方向に主鉄筋同士が離れており、しかも通常の施工方法では外側の主鉄筋も取り囲む帯鉄筋の配置が出来ない。また、コンクリートは掘削泥水中で打設される。そこで、帯鉄筋で囲まれていない重ね継手の性状を調べるため、鉄筋籠を掘削用の泥水中に24時間以上漬け込んだ後、コンクリートを打設した梁部材を21体作成し、曲げせん断試験ならびに純曲げ試験を行った。さらに、地中に実際に造られた地下連続壁の一部を切り出して造られた梁部材7体の載荷試験結果についても考察した。その結果、通常の方法で製作された試験体に対して提案されている既往の式による耐荷力の計算値に比較して、今回の試験体ははるかに弱いことが確認された。重ね継手長・主鉄筋の直径・主鉄筋間のあき等の各種パラメータが継手の耐力に与える影響については、Jirsaらの式の適用性がもっとも高いことを示した。また、このような重ね継手の場合、梁部材に作用するせん断力が継手の耐力に大きく影響することも併せて示した。以上の研究結果から、帯鉄筋に囲まれていない重ね継手の耐力を算定する(3)式を作成した。  ここに、 :継手部コンクリート単位面積あたりの平均せん断強度 :継手部コンクリート単位面積あたりの平均せん断強度   :実験値より算定した引張り主鉄筋の平均総引張り力 :実験値より算定した引張り主鉄筋の平均総引張り力  cu:コンクリートの圧縮強度(最大280kgf/cm2)。実際の地下連続壁においては、コンクリート圧縮強度 cu:コンクリートの圧縮強度(最大280kgf/cm2)。実際の地下連続壁においては、コンクリート圧縮強度 cの0.7倍とし、かつ、245kgf/cm2以下とする。 cの0.7倍とし、かつ、245kgf/cm2以下とする。 b:梁の幅 h:梁高 l:継手長 e:梁に働く斜め引張り応力が、継手コンクリートに働く斜め引張り応力と同一方向の場合 -1,打ち消す方向の場合 +1,純曲げの場合等 0とする(即ち、t≧-5cmのときe=-1,t≒40cmのときe=0,t<80cmのときe=+1)。 Pu:最大荷重(kgf) また、帯鉄筋に囲まれた連壁剛体基礎の重ね継手の耐力を調べるため、上記と同様の方法で11体の梁部材を作成し、曲げせん断試験を行った。この結果、梁が十分なじん性を発揮するには、重ね継手区間内に水平主鉄筋の1.4倍以上の帯鉄筋を配置する必要があることを確認した。 (4)青森ベイブリッジの連壁剛体基礎に、考案した「水平主鉄筋の接続方法(特許第1792646号)」の一部をなす継手金物として、片側にスリットををもちその反対側に鋼板を取り付けられた厚肉パイプ(外管)に、一方に鋼板を取り付けた充填鋼管(内管)を嵌合させ、内管と外管の間にセメントミルクを注入する方法(パイプ継手、図2)を採用することとした。そこで、外管の外径・肉厚、内管直径、内管と外管の相対位置をパラメータとする30組の試験体を造り、引張り試験を行い、その耐力・変形性状に付いて研究した。試験の対象としたパイプ継手(外管外径100〜140mm)の見かけの降伏荷重は、継手の抜出し量が4〜5mmに達したときに生じる。内管と外管の相対位置の影響については、内管が外管開口部に偏心せずに接している場合の耐力が、内管が外管の中央にある場合よりも大きいことが判明した。また、外管における最大応力は鋼板取り付け位置から45°〜67.5°の位置に生じる。内管の抜出しに伴い外管開口部端を通り内管表面に接する滑り面が生じると仮定して、力の釣合からパイプ継手の降伏荷重を概ね算定できることを示した。  図2 パイプ継手 図2 パイプ継手 また、パイプ継手を用いた梁部材についても曲げせん断試験、高応力繰返し試験を行った結果、継手の無い試験体に比べてわずかにたわみが大きいものの繰返しによる剛性の低下も見られず、また耐力も低下しないことが確認された。 以上、本研究では連壁剛体基礎の設計に関して各種の実験・研究を行い、その成果として国内で最大級のPC斜長橋の主塔基礎に実用化された。 |