| 内容要旨 | | アルカリシリカ反応(ASR)による被害が顕在化した1980年代以降,我国においても本件に関する活発な研究がなされ,有益な知見が集積されている。しかし,ASRの進行を予測する手法は未だ確立していない。ASRの進行には極めて多くの要因が関与し,総アルカリ量や骨材量などの配合要因の些細な変動によってASRの進行に大きな差が生じる。本研究では,ASRの化学反応進行速度を,これを決定する多数の要因の関数として定式化(モデル化)したものである。また,上述の化学反応進行モデルによる計算結果(化学量)から,物理量であるコンクリート・モルタルの膨張量を求めるモデルも示した。 ASRは,コンクリート中のペースト部から骨材内部へのアルカリの進入によって開始される。基本的な化学反応速度を示すモデルは,アルカリの進入速度が拡散則に支配されるとした,下式に示すような拡散律速に基づくモデルである。  ここに,Daは骨材内部におけるアルカリの拡散係数(cm2/hr),tは時間(hr),Cはアルカリ濃度(mol/L)を示す。 最も重要な要因である骨材の反応性は,拡散係数の相違として表現される。また,アルカリ量,水/セメント比,単位水量の配合要因は,界面における初期アルカリ濃度(C0)を決定する要因として考慮されている。式の右辺第2項は骨材内部におけるアルカリの消費を示すが,速度は無限大である。ただし,単位量あたりの骨材がアルカリを消費する容量,および単位量あたりのシリカの溶出に要するアルカリ量(アルカリの消費効率)が骨材種類毎に異なる。なお,反応の進行に伴い系のアルカリ濃度が低下することは明かであり,濃度低下が常に次の反応速度(アルカリ進入速度)に反映される非線形モデルとなる。 式(1)を離散化して,骨材表面からの完全反応層の厚さx(cm)が求められる。図-1に,モデルによるxの計算結果と溶出試験による実測値を比較して示す。  図-1 完全反応層の厚さ計算値と実測値の比較 図-1 完全反応層の厚さ計算値と実測値の比較 これより,計算結果が実測値を良く再現できることがわかり,ASRの進行が拡散律速理論に基づくモデルで十分に表現できることが示された。骨材を球形と仮定して半径の相違毎に骨材の体積反応率 iを求めることにより,下式によって単位コンクリート,モルタルあたりのシリカベースでの反応生成物総量Ts(mol/L)を求める事ができる。 iを求めることにより,下式によって単位コンクリート,モルタルあたりのシリカベースでの反応生成物総量Ts(mol/L)を求める事ができる。  ここで,Vaは単位反応性骨材量(cm3/L),Vsは全骨材に占める反応性成分(シリカ)の体積分率(-), は全骨材に占める半径Riの骨材の体積分率(-), は全骨材に占める半径Riの骨材の体積分率(-), sは反応性シリカの比重(g/cm3)をそれぞれ示す。本式には反応性骨材量および粒度分布が考慮される。 sは反応性シリカの比重(g/cm3)をそれぞれ示す。本式には反応性骨材量および粒度分布が考慮される。 次に,計算された反応生成物量から膨張量を求めるモデルを示す。骨材周囲のペースト部がバルクセメントペースト部に比較してポーラスであることが指摘されている。これより,骨材の表面積に比例する量の反応生成物が骨材周囲の細孔に吸収されて,膨張に寄与する反応生成物量を低減すると仮定した。 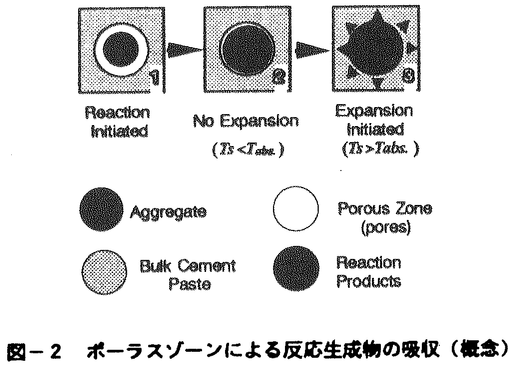 図-2 ポーラスゾーンによる反応生成物の吸収(概念) 図-2 ポーラスゾーンによる反応生成物の吸収(概念) また反応生成物量計算値と膨張量の関係が,反応生成物量側に切片を持つ直線関係となることが明かとなった。これより,膨張量を求めるモデルは下式のようになる。  ここで, は膨張量(%),aeは膨張寄与反応生成物量を膨張量に換算する係数,Tabs.は骨材周囲に吸収されて膨張に寄与しない反応生成物量(mol/L)を示す。このモデルによって,従来は解明不能であったペシマム現象(ある条件でASRによる膨張が最大になる現象)や,膨張前の潜伏期間などの複雑な膨張挙動が再現されることを明かとした。次図は,モデルによって再現されたペシマム現象の一例である。 は膨張量(%),aeは膨張寄与反応生成物量を膨張量に換算する係数,Tabs.は骨材周囲に吸収されて膨張に寄与しない反応生成物量(mol/L)を示す。このモデルによって,従来は解明不能であったペシマム現象(ある条件でASRによる膨張が最大になる現象)や,膨張前の潜伏期間などの複雑な膨張挙動が再現されることを明かとした。次図は,モデルによって再現されたペシマム現象の一例である。  図-3 モデルによって再現された反応性骨材量のペシマム 図-3 モデルによって再現された反応性骨材量のペシマム 最後に,本研究で示したモデルの考え方に基づき骨材の反応性を判定する新しいシステムを提案した。本システムは,(1)経時的な溶出試験による諸元の決定,(2)モルタルバー条件での反応生成物総量Ts(mol/L-mortar)の計算,(3)Tsと基準の比較による判定,の手順から成る。溶出試験を試験法として用いることにより,短期間での判定が可能である。システム判定基準は,フィールド試験との相関が高いモルタルバー法における膨張量の基準を考慮して決定している。このため,本システムは化学法とモルタルバー法双方の長所を有する。 |
| 審査要旨 | | コンクリート構造物を劣化させる要因には様々なものが存在するが、アルカリシリカ反応は、主にコンクリート中のセメントから供給されるアルカリと骨材中のシリカ分との化学反応が原因となるもので、欧米諸国においても1940年以来大きな問題として指摘されている。我が国でも1980年代以降、重要な劣化問題として位置づけられるようになり、その機構や劣化対策に関する研究が数多く行われている。しかし、アルカリシリカ反応の問題は複雑であり、従来の研究ではその劣化機構を定量的に説明することができないため、3カ月から6カ月の試験結果に基づき、そのつど対策を講じているにすぎない。本研究は、上記のことを考慮し、より定量的にアルカリシリカ反応によるコンクリートの劣化機構を明らかにするために、拡散律速理論に基づいたアルカリシリカ反応の進行を予測するモデルを提案するとともに、短期間で精度よく骨材のアルカリシリカ反応性を予測する新しい判定システムを提案したものである。 第1章は序論であり、本研究の位置づけとアルカリシリカ反応のモデル化の必要性を説明している。 第2章では、アルカリシリカ反応に関する既往の研究について概説しており、特に本論文で取り上げたアルカリシリカ反応の機構と、その進行に及ぼす要因に関する今までの研究による知見をとりまとめている。 第3章では拡散律速理論に基づく反応進行モデルを提案している。まず、化学反応過程におけるアルカリシリカ反応の進行がステファンモデルを用いて説明することができることを示しており、解析結果が骨材表面付近での微細組織観察結果とよく一致することを確認している。また、このモデルは、(1)骨材の反応性、(2)骨材の粒径分布、(3)単位骨材量、(4)単位水量、(5)単位セメント量、(6)アルカリ総量の配合要因の影響を評価することができることを示している。 第4章では、第3章で説明したモデル中の未知数を決定するための方法について記述している。ここでは、従来実施されているASTMおよびJISに規定されている化学法に準拠した溶出試験を経時的に実施することで、骨材中のアルカリの拡散係数を求める方法を提案しており、さらにアルカリシリカ反応の進行がアルカリの拡散速度に支配されるとした第3章で提案したモデルの妥当性を明らかにしている。 第5章では、第3章で示した反応生成物量の値を用いたモルタルバーの膨張予測モデルを提案している。このモデルでは、反応性骨材の表面積が大きい場合に反応がかなり進行しても膨張がさほど大きくならないことを、骨材周辺の空隙が反応生成物をある量まで吸収できると仮定したもので、一般に報告されている実験結果を再現できることを明らかにしている。ここでは、骨材の反応性の相違や配合条件の相違がモルタルバーの膨張挙動にどのように影響しているかを解析によって説明し、反応性骨材量および反応性骨材粒径のペシマム現象をも説明できることを示している。 第6章では、遅延型膨張を示す骨材と収束型膨張を骨材との違いについて実験を実施し、遅延型膨張を示す骨材は反応途中で見かけの拡散係数が変化することを明らかにし、いずれの骨材の場合にも第5章で示したモデルが適用できることを明らかにしている。 第7章では第6章までの検討結果を踏まえ、アルカリシリカ反応を判定する新しい判定システムについてまとめている。このシステムは、短期間の経時的な溶出試験を利用してモルタルバー条件での反応生成物総量を求め、モルタルバーにおける膨張量の基準から求めた限界反応生成物量との比較によりアルカリシリカ反応による被害の可能性を判定するもので、従来行われてきた化学法とモルタルバー法双方の長所を有している。 第8章は、結論であって、本論文で得られた成果をまとめている。 以上を要約すると、本研究はコンクリート構造物のアルカリシリカ反応による劣化を防止するために、その反応機構を明らかにするとともに、ペシマム現象や膨張前の潜伏期間、遅延膨張などの複雑な膨張現象を定量的に予測する手法を明らかにしたものであり、さらに、従来では数カ月を要した骨材の反応性判定試験を数日間で実施する新しいシステムを提案したものであり、コンクリート工学の発展に寄与するところ大である。よって、本論文は博士(工学)の学位請求論文として合格と認められる。 |