耐震設計において、鉛直荷重を支持する構造骨組に、専ら水平(地震)荷重に抵抗しエネルギー吸収を目的とする機構(履歴型エネルギー吸収機構)を組み込む構造方式が考えられる。これは、常時の鉛直荷重を支持する骨組と水平荷重時の振動を抑制する機構の役割を明確に分離し、それぞれの要求性能に相応した骨組および減衰機構を合理的に設置することを意図した構造方式である。 この履歴型エネルギー吸収機構の考え方を耐震壁に適用したものが可撓耐震壁である。可撓耐震壁には次のような性能が要求される。 1) 骨組の中にあって載荷初期においては高い剛性を有し、比較的低いレベルの振動状態から塑性域に進入し、かつ高い靭性性能を有すること。 2) 性能評価において明快であること。 3) 建築物の諸機能と整合が取れること。 4) 生産性が優れていること(低コスト・短工期)。 以上の要求性能を満足させるべく筆者が提案し、いくつかの高層建築物に適用したものが鉄筋可撓耐震壁である。鉄筋可撓耐震壁とは「一枚の鉄筋コンクリート耐震壁を上下二つに分割して間隙を設け、その間にせん断力を伝達するための鉄筋を櫛の目状に挿入し、その曲げ靭性にエネルギー吸収機能を期待した耐震壁」である(図1)。 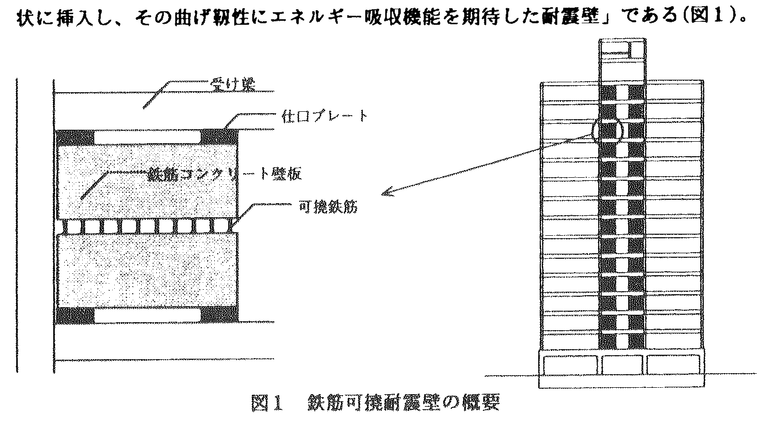 図1 鉄筋可撓耐震壁の概要 図1 鉄筋可撓耐震壁の概要 弾性である主体骨組と、塑性化を許容する履歴型エネルギー吸収機構としての鉄筋可撓耐震壁からなる骨組の計画において、効率よく部材を配置、設定をするには弾塑性応答性状を予測する必要がある。本論ではこの計画を効率良く行うための手法を提案し、そのための弾塑性応答性状の定式化を計った。 計画段階において、簡便に弾塑性性状を予測するには、個々の部材の性状ではなく、構造物全体の特性を評価できる簡略化されたモデルが必要となる。設計方針として主架構は弾性に留め、鉄筋可撓耐震壁は早期に塑性化させることを意図しており、解析にあたって鉄筋可撓耐震壁を有する骨組は、弾性である主体骨組と塑性化を許容する鉄筋可撓耐震壁とに分類して考える。すなわち、鉄筋可撓耐震壁の復元力特性を完全弾塑性モデルとして扱うことにより、鉄筋可撓耐震壁を有する構造物を弾性部材と完全弾塑性部材の和としてモデル化する(図2)。 一方、弾塑性応答の予測については次のように考える。ある特定の地震波を用いて時刻歴弾塑性応答解析を行った結果は、入力地震波の影響を受けており、その構造物の一般的な耐震性を把握するには適切でない。そこで、設計用入力地震動としては地震動の不確定要素を考慮し、包絡的な弾塑性応答を示す地震動を採用する。その応答予測に関しては、地震による入力エネルギーと構造物の吸収エネルギーとの関係から構造物の損傷や変形状態の定量的評価が可能であることが秋山博士により報告されている。本論ではこのエネルギー入力に着目して弾塑性応答を予測する手法を採用する。 すなわち、まず、弾性部材と完全弾塑性部材からなる骨組の1質点バイリニアモデルによる応答解析を行い、地震総入力エネルギーと累積損傷エネルギーの関係、累積損傷エネルギーと平均累積塑性変形倍率、最大応答変形および塑性変形倍率の関係を定式化する。次に、多質点系モデルでの各層の損傷集中度の定量化を計る。この定量化の方法は、最適降伏せん断力係数分布とそれからの隔たりの度合いにより損傷集中を予測する秋山博士の提案した手法を、第2分枝剛性が存在する場合に展開する方法である。この定式化のなされた予測式により主架構と鉄筋可撓耐震壁に対する要求性能を確定し、その要求を反映した具体的部材を有する骨組の設計手法を構築する。 以下に、各章の概要を述べる。 第2章においては、鉄筋可撓耐震壁を有する骨組を1質点等価せん断型弾塑性モデルとして表現し、周波数依存性の小さな応答スペクトルを有する模擬地震波に対する応答性状に関して以下のことを把握した。 累積損傷エネルギーの総入力エネルギーに対する比は、降伏せん断力の弾性時最大応答せん断力に対する比と剛性低下率を用いて予測可能である(図3)。また、平均塑性変形倍率と平均累積塑性変形倍率の関係は、極端に剛性低下率が低い場合を除き剛性低下率に依存しない。さらに、範囲を限定すれば塑性率の正側と負側の片寄りは簡単な係数により表すことができ、平均塑性率から最大応答変形が予測可能である。 これらの関係を定式化した予測式を用いて、累積損傷エネルギー、累積塑性変形倍率および最大応答変形を構造減衰の影響を考慮した形で予測することが可能であり(図4)、予測値と時刻歴応答解析結果が良い対応となることを示した。 以上より、1質点等価せん断型モデルの弾塑性応答性状をエネルギー論的立場から予測可能であることを明らかにした。  図表図2 復元力特性図 / 図3 EDlast/Elast(h=0.02) / 図4 1質点系応答予測図 図表図2 復元力特性図 / 図3 EDlast/Elast(h=0.02) / 図4 1質点系応答予測図 第3章においては、鉄筋可撓耐震壁を有する骨組を多質点等価せん断型弾塑性モデルとして表現し、周波数依存性の小さな応答スペクトルを有する模擬地震波に対する応答性状に関して以下のことを把握した。 各層の平均累積塑性変形倍率が一定となる最適降伏せん断力係数分布からの降伏せん断力の隔たりの度合いを用いて、各層の累積損傷エネルギー分布が予測可能である。また、多質点弾塑性系への総入力エネルギーは1質点系と本質的な差異はなく、総累積損傷エネルギーの総入力エネルギーに対する比率も1質点系の予測値から推定できる。最大応答変形に関しては、1質点系で提案した平均塑性変形倍率と平均累積塑性変形倍率の関係式を各層毎に適用可能である。 これらのことより、多質点等価せん断型弾塑性系の応答が、1質点系の応答予測式と損傷分布の予測式を用いて予測可能であることを示した。また、第2分枝勾配の応答結果に与える影響は小さく、降伏せん断耐力比の変化が応答結果に対して支配的であることを示した。 以上より、鉄筋可撓耐震壁を有する架構の多質点等価せん断型モデルの弾塑性応答性状は、エネルギー論的立場から予測可能であることが判った。 第4章では、「弾性である主体骨組と完全弾塑性系で表せる鉄筋可撓耐震壁からなる骨組に対しては、第2、3章で定式化された応答予測方法が適用できるので、鉄筋可撓耐震壁に要求される剛性と降伏耐力を地震時総入力エネルギーとの関係で評価することが可能となる。」という観点から、以下に示す設計法を確立した。 まず、1質点応答予測図を用いて、可撓鉄筋の許容累積塑性変形倍率を満足するように目標としての降伏せん断耐力比および剛性低下率を設定する。同時に、最大応答変形に関して弾性時に対する弾塑性時の比が設定されることとなり、弾性時における各層の目標層間変形角が求まる。 次に、各層の弾性時目標層間変形角となる初期剛性分布を、設計用地震波のエネルギースペクトルを用いてスペクトルモーダル解析により求める。各層の目標降伏せん断力は、目標とする降伏せん断耐力比が算定されているので、最適降伏せん断力係数分布を用いて設定することができる。 これらの目標値と鉄筋可撓耐震壁の剛性および耐力の選択範囲に基づき、各部材を実用性などをも考慮して配置する。 このようして部材配置された各層の降伏せん断耐力は、最適値から隔たりを生じる。そこで、損傷集中則に従って各層の応答予測を行い、各層の累積塑性変形倍率と最大層間変形が設計目標内であるか否かの判定を行う。不都合が生じた場合には、部材配置へ戻ることとする。 以上より、従来時刻歴弾塑性応答解析によって試行錯誤的に決定されていた鉄筋可撓耐震壁を有する架構の部材配置を、エネルギー論的予測手法を用いて簡便に設定することができる。 第5章では、上記の手法を適用して15層建物の設計を行い以下のことを確認した。 すなわち、最適降伏せん断力分布を目標とし、層の降伏せん断力を主体に部材を調整する第4章の計画法によって設定した鉄筋可撓耐震壁を有する骨組の部材は、設計目標をほぼ満足していることを時刻歴応答解析と対比することにより確認し、計画法の有用性を示した。 以上を通じて、鉄筋可撓耐震壁を有する架構の特性を明らかにした上で、主架構と鉄筋可撓耐震壁とをそれぞれ適正に設定するための設計法を提示した。 なお、この方法は他の履歴型エネルギー吸収機構を持つ骨組に対しても適用し得る一般性を有するものである。 |