鎌倉時代には鎌倉の幕府、京都の朝廷、二つの支配機構が並存していた。これらを子細に検討することは、日本の中世を研究するに必要不可欠な作業であろう。このうち幕府については多くの言及が為されているが、朝廷についてはいまだ具体的な全体像すら把握されていない。本論は朝廷を主題とし、訴訟制度に注目しながら、公家政権の分析を試みる。 ここで言う訴訟とは、現行の裁判のみを意味しない。除目で「(忠定が昇進した。)父卿一日之中三度被申訴訟之由、仍被仰切了」(『明月記』嘉禄二年正月十三日)といわれるように、朝廷の自覚的な判断を迫る行為を指している。現代の立法・行政・司法(狭義の訴訟)に該当する行為は、広義の訴訟への応答として現れる。 しかし狭義の訴訟と広義の訴訟は決して無関係ではありえない。当時、司法行為は法を定めることや政務を行うことと分かち難く行われていて、狭義の訴訟に関与する人々がそのまま広義の訴訟の担い手となっている。裁判官は官僚でもあり、政治家も兼ねている。狭義の訴訟の制度の整備は自覚的な判断を下す機構の整備であり、朝廷という支配機構の整備に等しい。本論は中世の朝廷の訴訟制度を特に「朝廷訴訟」とよび、その働きを明らかにするものである。 (1)朝廷訴訟の構造 朝廷訴訟は蔵人・弁官(両者を併せて奉行という)への訴の提起によって始まる。奉行は奏事目録を作成し、伝奏を通じて上皇の指示を仰ぐ。訴陳を番えるならば奉者となって院宣を書き、訴状・陳状の応酬を促す。それでも争いが解決しないと評定衆・文殿衆の意見が求められる。評定衆は公卿、文殿衆は下級の実務官で構成されている。上皇は彼らの意見を十分に考慮して、最終的な裁定を下す。彼らの位置関係を図示すると次のようになる。 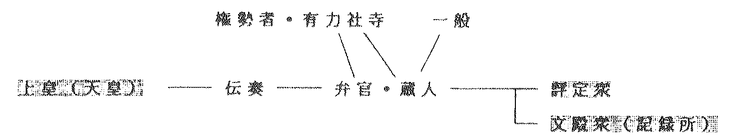 図表 図表 評定衆はA上級廷臣とB中流廷臣とに分類され、伝奏はB評定衆と出自を等しくする。伝奏とB評定衆は、平安末期以来院政を支えていた練達な実務官によって占められていた。彼ら「名家」の人々は蔵人・弁官を務めた後に伝奏・B評定衆に補されるのであり、彼らこそが朝廷訴訟の担い手であった。 一方、令制での高い官位を根拠として朝政を指導してきた摂関家と清華の人々は、わずかにA評定衆に任じられるのみである。上卿層の実務からの乖離、院宣の隆盛、陣議の形骸化などからすると、鎌倉時代の朝廷訴訟は、摂関や清華の力を排除した、新たな朝廷の制度であった。この変化はどのような経過を経てもたらされたのか。本論は鎌倉時代初頭に遡り、この問題を考える。 (2)九条兼実の執政と後鳥羽院政 朝廷の指導者としてまず登場したのは、源頼朝と結んだ九条兼実である。兼実は伝統的な公卿の合議を重視して議奏公卿を設置し、記録所を再興して訴訟にあたらせた。両者は治天の君たる後白河上皇を掣肘するものとして働き、恣意的な専制を行う上皇と対立する役割を課せられていた。訴5制の整備を試みる兼実の真の対抗者は、代を重ねて強大になった上皇であり、それゆえに武力の統括者である頼朝の援助を失うと、直ちに失脚を余儀なくされた。 後白河上皇の後継者として院政を布いたのは後鳥羽上皇であった。上皇はまず記録所を摂関から切り離して自ら統括し、また自己の周囲に議奏公卿の系譜を引く特定の公卿を召集して朝事を議論させた。朝廷訴訟の主催者としての地位を回復した上皇は、やがて記録所・公卿議定の役割を低下させ、代わりに近臣を登用して訴訟にあたらせた。訴訟の制度的な運用は停滞し、上皇の側近くに位置する者のみが訴訟の機会を与えられるようになった。政務のみならず訴訟においても、上皇による専制が行われたのである。 (3)承久の乱の史的位置 後鳥羽上皇は有力御家人を北面・西面の武士として編成し、幕府を介さずに、軍事活動に従事させていた。南都北嶺と戦い、京都御所の警護にあたる彼らの内には、西国の守護が多く含まれていた。上皇は彼らの力を利用して鎌倉幕府の討伐を図る。これが承久の乱である。しかし西国の守護は任国にいまだ十分に根付いておらず、東国の守護ほどには任国の武士を戦場に動員できなかった。京方と鎌倉方の兵力差は甚だしく、朝廷は完敗を喫してしまう。戦勝者たる幕府側の規範に従って後鳥羽上皇ら三人の上皇は配流され、上皇の多くの近臣が処刑された。この厳しい眼前の事実は朝廷の権威を根底から覆した。これ以後朝廷は天皇の交替にすら幕府の許可を仰ぐようになった。あわせて朝廷は、これ以後独自の軍事力の保有を禁じられた。精神的にも現実的にも朝廷の強制力は一気に低下し、それゆえに上皇の威光を基礎とした朝廷訴訟は、新たなあり方を模索する必要に迫られる。 (4)九条道家の執政 承久の乱後、後高倉上皇と近衛家実が施政者として登場するが、彼らの時期にさしたる変革はみられない。顕著な変化が認められるのは九条道家が摂関の地位に就いてからである。彼は実務に堪能な人々を「顧問に預かる輩」として組織した。才能・勤勉・家格という三つの価値のうち、彼らは特に才能を重んじ、評定を重ねて道家の諮問に応えていた。道家は施政の眼目として訴訟を広く行うこと、任官叙位を正しく行うことを挙げているが、彼の方法は、 正しい授官を行って名家の人々を登用する→訴訟制を確立し、合理的な訴訟を行う→人々の朝廷への信頼を回復する というものだったと思われる。 ただしこの方法には重大な欠陥があった。固有の軍事力をもつ大社寺の強訴が為された場合、一般的な合理制を基礎とする朝廷の調停作業は全く無力だったのである。このとき道家が頼みとしたのは幕府の軍事力であった。軍事力をもたぬ朝廷は、支配機構としての実を示すため、幕府の援助を必要とすることがあった。そのために援助の要請を行える者こそが廟堂で重んぜられた。子息頼経を将軍として鎌倉に送り、関東申次の職に就いて幕府との連絡を独占していた道家は、まさにその典型であった。 (5)後嵯峨院政 九条道家の権力の高まりは、将軍頼経の存在と相まって、北条得宗家の警戒するところとなった。四条天皇が急死すると、幕府は道家が強く推す忠成王を退け、後嵯峨天皇を即位させた。さらに名越光時の乱が起きると、幕府は頼経を鎌倉から追放するとともに、道家の関東申次の任を解いた。鎌倉との連携を断たれた道家は即座に失脚し、幕府の指示を得た後嵯峨上皇が院政を開始する。これが後期院政の始まりである。 後嵯峨上皇は上皇の補佐役たる伝奏をおき、また評定衆をおいて訴訟を管掌した。両者は共に名家の出身者で占められており、顧問の輩と評定衆の類似からすると、後嵯峨院政は道家の施政を継承したものといえる。上皇に課せられた命題は、訴訟の興行の主体として摂関を凌駕する、というものであった。上皇は建長年間頃にはこの課題を一応達成し、幕府と歩を一にしながら院政を進めていった。 (6)亀山院政 後嵯峨上皇が没すると、幕府の許可を得た上で亀山天皇が政治を行った。このとき、摂関家の力を結集した鷹司兼平が天皇の対抗者として台頭してきた。しかし兼平は幕府と交渉する方途を見いだせず、そのために訴訟制の頂点に座し得なかった。 亀山天皇はやがて上皇となって院政を布くが、弘安年間には文殿衆が組織され、評定衆と同様に訴訟案件を議定するようになる。文殿は治天の君が上皇である場合に記録所の機能を移した機関であって、ここに、はじめに記した上皇を中心とする朝廷訴訟の制度は完成を見たのである。 (7)持明院統・大覚寺統の治世 亀山院政は訴訟制の拡充を図る政策を次々に打ち出した。しかし霜月騒動で安達泰盛の一派が滅ぼされると、幕府は院政の停止を命じた。騒動の勝利者平頼綱が院政のあり方に危機感を抱いたためではなかろうか。これ以後、得宗の専制下にある幕府は、皇統の細分化、治天の君の座の相対化を図る。その上で治天の君を指名する者として、朝廷への優位を保とうとする。持明院・大覚寺両統の迭立と呼ばれる現象は、幕府の意思によって現出するのである。 治天の君の座が相対化したことは、上皇たちに施政に精励することを促した。彼らは有能な廷臣、とくに名家の人々の獲得に務め、朝廷訴訟を充実していった。こうした君臣の交わりの中から王権至上の考え方が生み出され、それはやがて倒幕活動に結びついていく。但し後醍醐天皇についていえば、父後宇多上皇との確執があり、訴訟を司る廷臣たちの協力を得られなかった。天皇の倒幕が成功した理由は、朝廷訴訟では説明ができない。建武親政の成立とその急激な崩壊により、朝廷訴訟はその命脈を断たれるのである。 |