| 内容要旨 | | 大規模な地震に対し建築構造物が倒壊せずに人命の安全を確保するためには,建築構造物のエネルギー吸収能力が必要であり,鋼構造建築物のエネルギー吸収能力を確保するためには,構成する部材が降伏後も耐力を維持し,十分な塑性変形能力を持つことが必要である。 鋼構造部材に塑性変形能力を確保しエネルギー吸収能力を保有させるためには,材料である鋼材には強度に加えて,降伏点の引張強度に対する比である降伏比YRが低いことと,鋼材の靭性が高いことが必要になる。YRが低ければ降伏してからの耐力上昇が期待できるので,地震時に応力が部材長さ方向に勾配をもつ柱・梁のような部材では降伏する範囲が広くなり,塑性変形量を大きくできる。また鋼材の靭性が高ければ,少々のきず・欠陥などがあっても破壊を避けられる。 しかしYRを低くすることと,強度を高くしかつ靭性を高くすることには,二律背反的ともいえる関係がある。総合的に耐震性能を高めるためには,どういう鋼材性能がどういう時に必要になるかをはっきりさせて,設計に利用してゆく必要がある。 本研究は,鋼材のYRと靭性が建築構造部材の耐震性能に与える影響を把握し,それぞれの鋼材性能の目標レベルを決めるための基礎データを得ることを目的として,鋼材性能を変えて製造した鋼板から試験体を製作して,部材実験を行っている。以下に,各章の研究内容と得られた知見を要約する。 第2章 試験材料 では,YRの目標値を変えて本研究用に製造した鋼板の,材料引張試験から得られたYRと,シャルピー衝撃試験で得られた衝撃吸収エネルギー・遷移温度の靭性指標とを比較している。また販売用に製造した鋼板についてYRとシャルピー衝撃吸収エネルギーの関係も比較している。YRと靭性は相関がほとんどなく,全く別々にきまる鋼材性能である。 第3章から第5章では3つの鋼種(SS400,SM490,SM570)と3水準のYR目標値(70%,80%,90%)の組合せと,幅厚比をパラメータとして部材実験を行い,幅厚比と降伏点の組合せである等価幅厚比が,部材の耐力上昇率・塑性率・エネルギー吸収能力の支配要因であることを確認している。また等価幅厚比の関数になるとして求めた実験式を用いてYRの影響を求めている。等価幅厚比は次のように定義している。 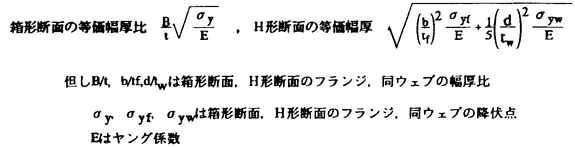 第3章 短柱圧縮試験 では,鋼材の鋼種・YRの組合せと幅厚比をパラメータとして,箱形断面とH形断面について,外径の3倍の長さの試験体で短柱圧縮試験を行った。 第4章 梁の曲げ実験では,鋼材の鋼種・YRの組合せと幅厚比をパラメータとして,H形断面梁の曲げ実験を,載荷点支点間の細長比がほぼ10になる試験体を用い中央集中載荷で行った。 第5章 柱の圧縮曲げ実験では,鋼種・YRの組合せと幅厚比をパラメータとした箱形断面とH形断面の柱の圧縮曲げ断実験を,軸力比0.3の軸力を試験体両端にかけた状態で中央集中載荷で行った。 鋼材の降伏点が高くなるほど短柱圧縮試験の最大応力度は高くなる。しかし降伏点が高くなるほどには最大応力度は高くならない。従って最大応力度の降伏点に対する比である応力上昇率にはYRの効果が現れ,降伏点が低くYRの低いほうが応力上昇率が高くなる。梁と柱についても鋼材の降伏点が高くなるほど曲げ耐力は高くなるが,降伏点が高くなるほどには最大応力度は高くならない。従って降伏点で曲げ耐力を規準化した耐力上昇率にはYRの効果が現れ,降伏点が低くYRの低いほうが耐力上昇率は高くなる。 箱形断面については,応力上昇率並びに耐力上昇率が等価幅厚比の平方根に反比例するとして求めた実験式と実験値との相関係数は0.95以上と高い相関が得られている。これらの実験式を用いてSM490-YR70とSM490-YR80との差を求めた。短柱の応力上昇率の差は,同一等価幅厚比に対し6%程度,同一幅厚比に対して9%と,実測したYRの差11%よりは小さい。 H形断面のSM490-YR70とSM490-YR80とについても同様に,応力上昇率・耐力上昇率が等価幅厚比の2乗に反比例するとして求めた実験式から求めると,短柱と梁では鋼板の実測YRの差がそれぞれ9%と10%であるのに対し,同一等価幅厚比での応力上昇率・耐力上昇率の差は5%程度と低い。柱では等価幅厚比0.5において,鋼材のYRの差と耐力上昇率の差がほぼ等しくなっている。このように応力上昇率と耐力上昇率に関してはYRの効果は見られるが,その程度の差はYRの差よりは小さい。 短柱の塑性率は,等価幅厚比の2乗に反比例するとした実験式と実験値との相関係数は,箱形断面が0.99,H形断面が0.89であり,SM490-YR90のH形断面を除くとYR単独の影響は見られない。 H形断面の梁と箱形断面の柱では,等価幅厚比の3乗に反比例するとした実験式と実験値との相関係数はそれぞれ0.98と0.96でありYR単独の影響は見られないが,H形断面の柱では等価幅厚比0.5においてYRの差の1.5倍塑性率の差がある。引張強度一定の条件で実験式から求めると同一幅厚比に対しH形断面の梁と箱形断面の柱では,YRの差10%に対し塑性率の差は18%となる。 引張強度で規準化した部材のエネルギー吸収能力が等価幅厚比の3乗に反比例するとして求めた実験式と実験値との相関係数は,H形断面梁が0.96,箱形断面柱が0.98,H形断面柱が0.93といずれも高い相関を示している。これらの実験式を用いて計算すると同一幅厚比の条件では,YRの差10%に対しエネルギー吸収能力の差は18〜23%であり,差はあるが大きくはないといえる。 H形断面の軸力比が0.0の梁と0.3の柱では,同一等価幅厚比である断面の塑性率の比が2.5倍〜4.5倍程度になり,変形能力の差は大きい。軸力比が小さくウェブの一部が引張になる場合は純圧縮の場合と比べ局部座屈に対し有利になるので,有効幅厚比は小さくなる。軸力比が0.0の有効幅厚比は軸力比0.3の有効幅厚比の0.75倍なので,実験式から塑性率は2.4倍になり,有効幅厚比である程度説明できている。箱形断面については,軸力比0.0の有効幅厚比は軸力比0.3の有効幅厚比の1/1.21なので,実験式から塑性率とエネルギー吸収能力は1.8倍になる。 YRの差が20%でもエネルギー吸収能力の差は高々40%であり,YRは効果はあるが軸力比ほどの影響はない。変形能力・耐力・部材エネルギー吸収能力の支配要因は等価幅厚比であり,軸力比も重要な要因である。YRの影響はみられるが大きなものではない。 第6章〜第8章では鋼種SM490の実大試験体で,正負交番繰返し載荷を主体とする部材実験を行い,脆性破壊と,歪履歴・鋼材の靭性との関係を調べている。 第6章 実大箱形断面柱曲げ実験ではSM490の□-800*40の実大サイズの箱形断面柱の曲げ実験を実施している。6体中1体は負側のサイクルで亀裂が進展して荷重が低下したため終了しているが,その前の負側のサイクルで亀裂が発生した後も耐力は上昇している。この他に亀裂が発生した試験体と,人工欠陥をいれた試験体が各1体あったが,ウェブの局部座屈により最大耐力が決まっている。塑性率はいずれも8を超えている。 破壊しなかった原因は,引張側のスケルトン歪を用いて求められるCTOD値と比べ,使用鋼材の破壊限界CIOD値が高かったためと推定できる。 第7章 箱形断面柱・H形断面梁接合部載荷試験では,柱降伏先行型で柱梁接合部パネルを含む実大十字形部分骨組の繰り返し載荷実験を柱断面□-600*32梁断面H-1000*500*25*40で実施した。パネルと柱の耐力比,ダイアフラム形式を変えている。試験体6体のいずれについても変位角1/13まで安定した荷重-変形関係を示しており,累積塑性変形倍率は10〜15と変形能力は大きかった。その後の繰返し回数は試験体によって異なるが,5体が脆性破壊した。変形能力とエネルギー吸収能力では,梁貫通型が柱貫通型より10%程度高くなっている。柱側の破断で最終状況が決まる条件では,梁端が広く柱側の応力が緩和される梁貫通型のほうが破壊しにくいといえる。歪が大きくなりCTOD値が鋼材の破壊限界CTOD値を超えたため破壊したと考えられる。 第8章 低靭性材での箱形断面の曲げ実験 では,CTOD破壊条件を全塑性状態での繰り返しをうける建築構造用部材にも適用できるかを検証する目的で,低靭性の鋼材を用いて箱形断面の試験体を製作し,正負交番繰返し曲げ実験を3水準の板厚(22mm,40mm,80mm)について実施した。 試験体9体中5体が脆性破壊したが,脆性破壊しているのは載荷時の室温が鋼材のシャルピー衝撃試験の破面遷移温度より低い場合である。最終サイクルの引張側の歪を用いてCTOD値 を求め限界CTOD値 を求め限界CTOD値 Cに対する比0.9〜1.4未満では脆性破壊しないが, Cに対する比0.9〜1.4未満では脆性破壊しないが, / / Cが1.4を超えると脆性破壊するといえる結果が得られた。 Cが1.4を超えると脆性破壊するといえる結果が得られた。 塑性域での繰返し歪履歴による靭性の劣化を,載荷後の試験体で調べているが,累積塑性変形倍率10以上に相当する,引張側と圧縮側のスケルトン歪の和10%程度の歪履歴では,ほとんど靭性の劣化はない。しかしながら人工欠陥の先端のような歪集中部では,スケルトン歪の和が1〜2%でも靭性は劣化する。 この実験結果から,累積塑性変形倍率10程度の変形能力に相当する4.4%程度の引張歪を受け,等価欠陥寸法が1mm以下の亀裂または欠陥があっても脆性破壊しないためには,使用最低温度での Cが0.17mm以上あれば良いといえる。シャルピー衝撃試碑に換算すると使用最低温度+40℃での衝撃吸収エネルギーが170J以上となる。早期の脆性破壊を避けるためにはこのレベルの靭性が,鋼材・熱影響部・溶接金属に必要とされると考える。 Cが0.17mm以上あれば良いといえる。シャルピー衝撃試碑に換算すると使用最低温度+40℃での衝撃吸収エネルギーが170J以上となる。早期の脆性破壊を避けるためにはこのレベルの靭性が,鋼材・熱影響部・溶接金属に必要とされると考える。 |