脊柱側彎には、先天性側彎(骨の先天的形態異常によるもの)、麻痺性側彎(ポリオなどの麻痺性疾患にともなうもの)、症候性側彎(Marfan症候群などの結合組織疾患にともなうもの)、および基礎疾患のない特発性側彎などがある。症例の過半数を占める特発性側彎は、思春期に発症し進行することが多い。体幹の変形が進行すると、腰背痛や、胸郭容積の減少による拘束性呼吸機能障害を生じるので、側彎が中等度に達すると観血的治療が必要となるが、その方法は脊柱の矯正固定術であり、多数の椎間を固定するため、手術侵襲が大きく、脊柱の生理的な運動を犠牲にする点に問題がある。さらに固定椎間の隣接椎間に変性を生じ、腰痛や頚部痛の原因になることが指摘されている。特発性側彎の予防および根治的治療のためには、変形の発現機序を知る必要がある。筋の異常により脊柱側彎が発現することは確実である。たとえば体幹筋の麻痺をともなうポリオ後遺症患者には、いわゆる麻痺性側彎があらわれる。これが筋力の左右不均衡に起因することにも疑いの余地がない。特発性側彎において、筋力の左右不均衡と変形との間に因果関係があるかどうかは未知であるが、それを明らかにするためには、筋力と密接な関係にある筋の長さと変形との関係を知る必要がある。 特発性側彎の脊柱の三次元的変形は、前額面、矢状面、水平面にそれぞれ投影して観察することができる(図1)。前額面では椎骨の列は曲線状にたわみ、体幹の中心から離れる。これにともない、本来水平である椎骨の終板は左または右に傾斜する。水平軸に対して終板が左または右にもっとも大きく傾斜する2個の椎骨を終椎と呼ぶ。2個の終椎にはさまれる脊柱の部分を彎曲と呼ぶ。また、体幹の中心軸からもっとも遠く離れ、彎曲の頂点にある椎骨を頂椎と呼ぶ。矢状面の投影では、胸椎部において、しばしば、生理的な後彎(後方凸の彎曲)の減少がみられる。 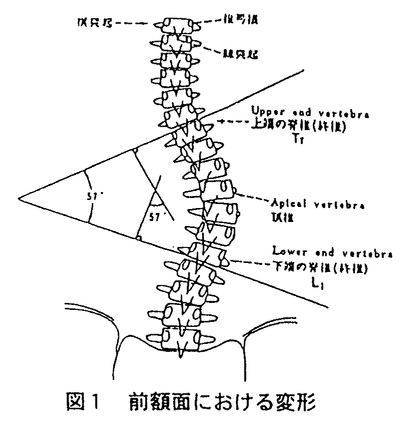 図1前額面における変形 図1前額面における変形 水平面の投影では、椎骨は、頭尾軸のまわりに、棘突起が彎曲の凹側を向くような方向に回旋する。たとえば、前額面で右凸の彎曲を構成する椎骨は、頭側から見ると時計回りに回旋している。この椎体の回旋は、躯幹全体の回旋を伴わない。すなわち、頭部と骨盤とがともに正面に向いた位置を保ったまま、脊柱に回旋変形が生じる。これが側彎症変形における回旋変形の特徴である。この回旋は頂椎部でもっとも大きく、彎曲の上端と下端で0となる。回旋が0である椎骨はふつうは終椎と一致する。すなわち、右凸の彎曲を頭側から尾側へとたどってゆくと、側彎が始まるとともに回旋が始まり、椎骨が体幹の中心軸から離れるとともに回旋が増加してゆき、頂椎でこれが最大となる。そして頂椎を境に回旋が減少し、尾側の終椎に至って回旋が0となる。ここで、隣接する椎骨間の位置関係を考えると、頂椎の頭側では、椎骨は尾側に隣接する椎骨に対して頭側から見て反時計回りに回旋した位置にあるが、頂椎の尾側では、椎骨は尾側に隣接する椎骨に対して時計回りに回旋した位置にある。すなわち隣接する椎骨間の、回旋を基準とした位置関係は、頂椎を境にして頭側と尾側とでは方向が逆転している。 上述のような特徴を持つ特発性側彎の脊柱変形を起こしうる筋は、一部の背筋群に限られる。背筋には脊柱と脊柱以外の部分、すなわち脊柱と骨盤との間や脊柱と上肢帯との間を結ぶ筋と、椎骨と椎骨との間を結び、各椎骨間の位置関係だけを局所的に変える筋、すなわち固有背筋とがある。前者の筋力によって彎曲が形成されるとすると、骨盤や肩が変形部分に含まれるため、上述のような、頭部と骨盤とがその位置関係を保つという、特発性側彎の回旋変形は生じえない。 特発性側彎の回旋変形が筋力によって起こるとすると、後者すなわち椎骨を個別に回旋させる固有背筋が作用しなくてはならない。幾何学的に考えるとその筋は椎骨の外側部を別の椎骨の正中部に連結する筋群でなくてはならない。これに該当する筋に、3椎間から6椎間をへだてた二つの椎骨を連結する多裂筋がある。 多裂筋の起始は、腰椎部では乳頭突起、下位胸椎部では乳頭突起に相当する小突起、中・上位胸椎では横突起の基部にあり、その停止は3椎間から6椎間をへだてた頭側の椎骨の棘突起の先端付近の側面にある小突起にある。多裂筋が収縮すると、上述の起始と停止との距離が短縮する。すなわち頭側の椎骨の棘突起すなわち正中部が尾側の椎骨の乳頭突起または横突起すなわち外側部に接近する方向に力が作用するので、椎骨の間に側彎(側屈)と前彎(前方凸である彎曲)が生ずるとともに回旋が生ずる。 したがって筋と特発性側彎との因果関係を明らかにするためには、多裂筋と特発性側彎の脊柱変形との関係を知ることがきわめて重要であり、筋の緊張が筋の長さと密接な関係にあることから見て、特発性側彎において左右の多裂筋の解剖学的長さを知ることが不可欠である。もし多裂筋の緊張の左右差によって側弯が生じているのであれば、筋の長さの左右差と、回旋を含む脊柱変形の程度との間には一定の相関があると考えられる。そこで、三次元CTを利用して、多裂筋の起始と停止間の距離を測定し、第一に、多裂筋の筋長の左右差の有無、第二に、筋長の左右差と脊柱変形との関係を検討した。 12歳-17歳の特発性側彎10症例(男性2例、女性8例)を対象とした。うち3例は二つの側彎をもつ、いわゆる二重側彎であったので、彎曲数は13個となった。各症例に上位胸椎から腰椎部までスライス厚5mm、スライス間隔5mmでCT撮影をおこない、東芝製診断用画像処理装置TDS-02Aを使用して三次元画像を作成し、多裂筋の起始と停止とを三次元画像上で求め、それらの座標値から両者間の直線距離をもとめ、これを筋長の測定値とした。筋長を測定した多裂筋の数は388対、1症例あたり34対-46対であった。 各彎曲は数個以上の椎骨から構成されており、これらに力学的作用をおよぼす多裂筋は多数ある。頂椎の、その高位と正中線からの変位の大きさによって彎曲の高位と変形とを表現できる、という重要性を考慮し、頂椎に対して力学的作用を及ぼすと考えられる一群の多裂筋を、その彎曲に関係する多裂筋とみなすこととした。これには、頂椎に起始または停止をもつ多裂筋計8対と、頂椎の尾側の椎骨から起始し、頂椎の頭側の椎骨に停止する多裂筋計14対との計22対ある。13個の彎曲に関係する計286対の多裂筋のうち、筋長が測定できた多裂筋は240対、1彎曲あたり8対-22対であった。各彎曲ごとに、彎曲に関係する多裂筋筋長の左右差の有意性をWilcoxon法によって検定した。いずれの彎曲においても凸側の多裂筋筋長が有意に大きかった(p<0.01)。 筋長を測定したすべての多裂筋について、それらが起始または停止する2個の椎骨間の側彎度と回旋度を以下のようにして測定した。すなわち、立位単純X線正面像において、一対の多裂筋が起始または停止する2個の椎骨の終板(頭側の椎骨は頭側、尾側の椎骨は尾側の終板)のなす角を測定し、これをその2個の椎骨間の側彎度とした。頭側の終板からみて時計回り方向を負、反時計回り方向を正とした。また、仰臥位で撮影したCT画像を用いて、各椎骨の椎体前方中央と椎弓後方中央を結ぶ直線とCT画像上の前後方向とのなす角を測定し、画像上での反時計回り方向を正とした。頭側の椎骨の回旋角度から尾側の椎骨のそれを減じて、その2個の椎骨間の回旋度とした。さらに、その2個の椎骨に起始または停止して、対をなす左右の多裂筋の筋長の比(右/左)をもとめ、上述の2個の変量すなわち側彎度および回旋度、との関係を解析した。 まず、各症例ごとに、前述の3個の変量のうち2個ずつをとった3個の散布図を作成した。いずれの症例においても、側彎度-回旋度の散布図は円形に近く分布し、側彎度と回旋度との間に、2乗の和が一定に近い関係があることを示した。側彎度-筋長比の散布図は直線状に分布し、側彎度と筋長比との間に一次的な相関があることを示した。これに対し、回旋度-筋長比の散布図は不規則に分布し、回旋度と筋長比とは無相関に近いことを示した。 さらに、筋長比(Y)を目的変数とし、側彎度(X1)と回旋度(X2)とを説明変数とした重回帰モデルY=a0+a1X1+a2X2を分析した。いずれの症例においても側彎度の回帰係数のF値の方が大きく(表1)、筋長比は回旋度よりも側彎度と強く相関することを示した。5%の危険率で回旋度の有意性が棄却可能である、すなわち、筋長比の変動に回旋度の変動が寄与しない、と言える症例が2例あった(表1中*)。 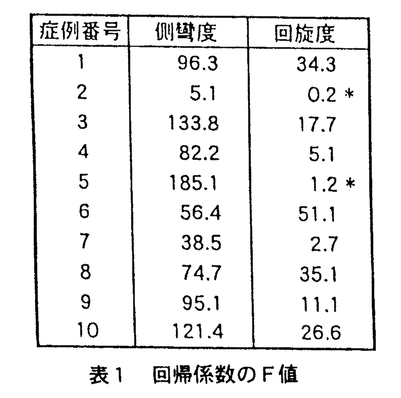 表1回帰係数のF値 表1回帰係数のF値 仮に、多裂筋筋力の左右不均衡が特発性側彎の脊柱変形を形成する一次要因であるとすると、椎骨間の回旋変形もまた多裂筋筋力の左右不均衡によって形成されることになる。さらに、筋の緊張と長さとの間に一定の関係があることを考慮すると、多裂筋の筋長の左右差が大きい部分では、それらの多裂筋が付着する2個の椎骨間の回旋変形も大きくなるはずである。しかし、本研究でえられた結果は、多裂筋の筋長の左右比と回旋変形との間に相関はなく、多裂筋筋力の左右不均衡が、特発性側彎の脊柱変形の一次要因であるとは考えにくい。 |