学位論文要旨
| No | 212993 | |
| 著者(漢字) | 上野,俊昭 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | ウエノ,トシアキ | |
| 標題(和) | 重力変化が脳循環に与える影響 | |
| 標題(洋) | Effects of Altered Gravity on Cerebral Circulation | |
| 報告番号 | 212993 | |
| 報告番号 | 乙12993 | |
| 学位授与日 | 1996.09.11 | |
| 学位種別 | 論文博士 | |
| 学位種類 | 博士(医学) | |
| 学位記番号 | 第12993号 | |
| 研究科 | ||
| 専攻 | ||
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 航空宇宙技術の発達に伴って、我々は過重力や低重力という1G以外の重力環境に遭遇するようになった。重力が変化した場合、静水圧の影響で身体の各部位での血管内圧も変化し、その結果さまざまな生理学的反応が引き起こされる。生理学的反応に関してこれまでの多くの研究は心循環系に焦点をあてて来たが、人体に対する安全性を考える上では心循環についてだけではなく脳循環についても検討する必要があると思われる。戦闘機パイロットが経験するような3G以上の重力負荷(意識消失を伴いうるレベル)はおそらく脳循環にも大きな影響を与えているはずであり、この点に関する報告も散見される。しかし、宇宙医学の観点から見ると、意識消失は通常生じない程度の重力負荷の影響を検討する方がより重要である。なぜならスペースシャトルでは、人体に最も影響を与えると考えられる体軸方向の重力変化の最大値は大気圏外からの帰還時の2Gであり、このレベルの過重力(平均は1.2G)が約20分程度続く。また、低重力の脳循環に与える影響も宇宙飛行の安全性を考える上では重要であろう。しかし、これまでそのような重力環境での脳循環についてはほとんど検討されていない。これは従来の脳循環の測定機器を過重力や低重力という特殊な環境で用いることが困難であるのが主たる理由であろう。そこで本研究では、近年開発された非侵襲的な脳循環測定装置(頸動脈ドップラー血流量計、トランスクラニアルドップラー、近赤外線分光計測装置)を用いて0Gから2Gの範囲での重力変化が脳循環に与える影響を検討した。 地上において1G以外の重力環境を作り出す方法はいくつかあるが、簡単な方法としては(1)被験者を臥位から立位に体位変換させる方法がある。また、(2)遠心加速装置を用いて過重力を作り出す方法もある。さらに、(3)下半身に陰圧を負荷して、過重力負荷時に生ずるblood shiftをシミュレーションする方法もある。(1)から(3)までは重力が増加する場合であるが、重力を減少させる方法としては、(4)飛行機より弾道飛行を行い約30秒間の無重力環境を作り出す方法がある。本研究では(1)から(4)まですべての場合における脳循環動態を検討し、重力変化が脳循環に与える影響を明らかにする。 (1)起立試験:2通りのプロトコールで行った。それぞれを起立試験Iと起立試験IIとする。起立試験Iは、7人の健康男性(平均21歳)を対象とした。被験者は電動ベッド上で臥位になり、測定値が安定した後、ベッドを30秒間かけて60度まで傾けその姿勢を15分間維持したのち、再び臥位に戻した(Fig.1)。また、起立試験IIは、8人の健康女性(平均20歳)を対象とし、1人の被験者につき15度、30度、45度、60度の起立試験をそれぞれ十分な間隔をとって行った。個々の起立試験のプロトコールは起立試験Iと同じである。起立試験I、IIともに、収縮期(SBP)、拡張期血圧(DBP)をマシシェット式自動血圧計で1分毎に、脈拍(HR)を心電図で連続モニターした。さらに総頚動脈血流量(CA)を頸動脈ドップラー血流量計で5分ごとに、中大脳動脈血流速度(MCA)をトランスクラニアルドップラーで4秒ごとに、脳組織内の酸化(OXY-Hb)および還元ヘモグロビン量(DEOXY-Hb)の変化を近赤外線分光計測装置で2秒ごとに測定した。 (2)遠心加速による過重力負荷:8人の健康女性(平均20歳)を対象とした。半径2.4mの遠心加速機を用いて1.5Gを30分間負荷した(Fig.2)。遠心力と重力の合成力の方向と被験者の体軸は平行となるようにしている。収縮期、拡張期血圧、脈拍を測定した。さらに脳組織内の酸化および還元ヘモグロビン量の変化を近赤外線分光計測装置で2秒ごとに測定した。 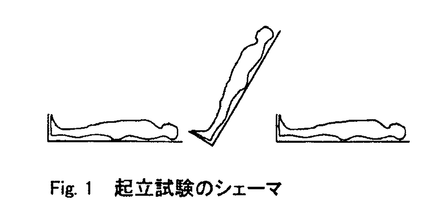 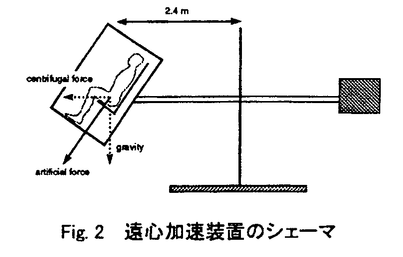 (3)下半身陰圧負荷:7人の健康男性(平均21歳)を対象とした。腸骨陵以下の下半身を密閉し、下半身に30mmHgの陰圧を25分間負荷した。測定項目は起立試験と同じである。 (4)飛行機での弾道飛行(パラボリックフライト):4人の健康人(男性2人、女性2人)を対象とした。1回の弾道飛行はFig.4に示したような経路で行われる。本研究では一人の被験者につき5-10分の間隔をあけて計6回行った。フィナプレス 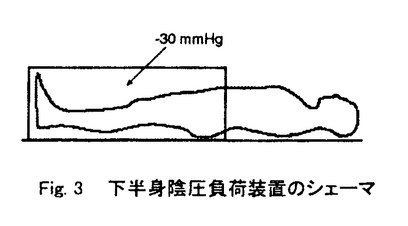 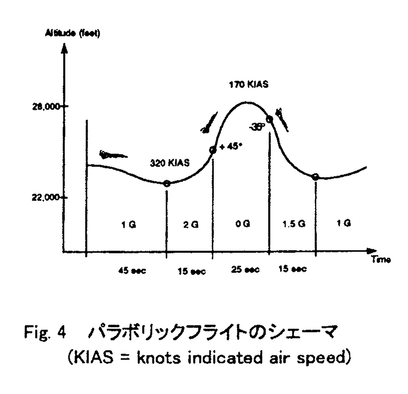 以下の表に示す。すべて平均±標準誤差で表示しており、それぞれの実験開始前の測定値と比べ危険率5%以内*または1%以内**の場合に有意な差があるとした。 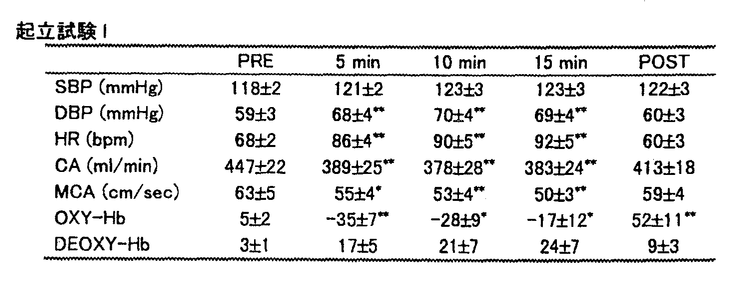 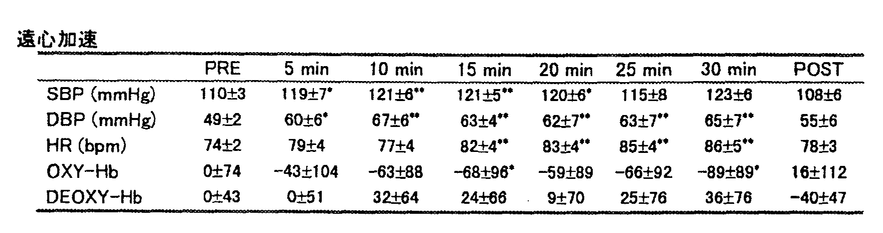 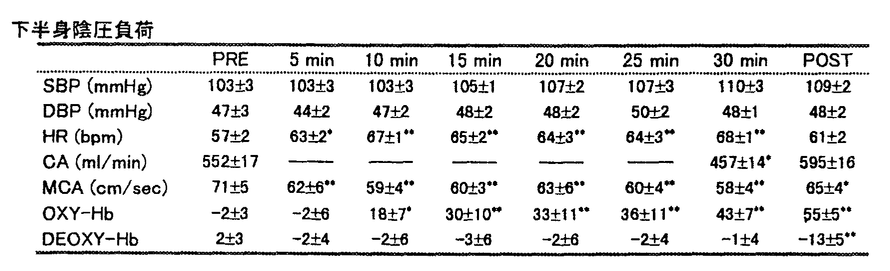 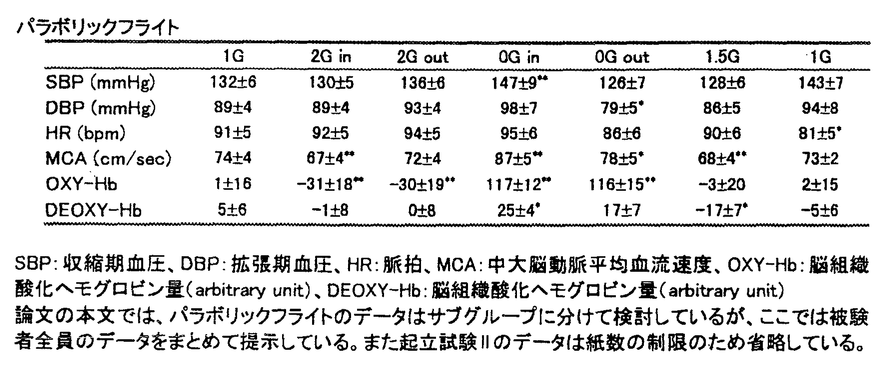 いずれの実験系においても過重力時には脳血液量(脳組織内の総ヘモグロビン量)は減少し、低重力時には増加している。これは、過重力時には静水圧の変化により頭部での静脈圧が減少し、低重力時には頭部の静脈圧が増加するためと考えられる。 また、以下に示すように、脳血流量は過重力で減少し、低重力で増加していると推察される。まず60度起立試験では総頸動脈血流量と中大脳動脈血流速度とは共に減少している。また、脳組織内酸化ヘモグロビン量は減少し還元ヘモグロビン量は若干増加している。これは脳組織内静脈血中の酸素飽和度(SvO2)が減少していることを示唆している。これまでの報告では姿勢変換で脳酸素代謝率(CMRO2)はほぼ一定とされているので、SvO2の減少は脳血流量(CBF)の減少を意味する(∵CBF=CMRO2/(1-SvO2))。いずれの測定方法も、直接、脳血流量を測定しているわけではないが脳血流量が減少していると考えるとすべての結果が矛盾なく説明可能である。次に遠心加速による1.5G負荷では、総頸動脈血流量と中大脳動脈血流速度とは測定していないが、脳組織内酸化および還元ヘモグロビン量の変化の傾向は起立試験時と同じであり、やはり脳血流量は減少していると思われる。下半身陰圧負荷時には、総頸動脈血流量と中大脳動脈血流速度とは共に減少しており、起立試験時や遠心加速時と同じく脳血流量は減少していると推察される。ところが、脳組織内ヘモグロビン量は、酸化ヘモグロビン量が増加を示しており、起立試験時や遠心加速時とは異なるパターンとなっている。脳血流量が減少しているとすると、この酸化ヘモグロビンのみの増加は動脈側で生じていると考えなくてはならない。すなわち、動脈側での血管拡張の結果、酸化ヘモグロビンが増加したと推察される。パラボリックフライトにおいては、中大脳動脈血流速度は過重力時に減少し低重力時に増加している。脳組織内ヘモグロビンについては還元ヘモグロビン量の変化に個人差があるが、脳循環モデル(詳細は論文のappendixに記述されている)を導入してヘモグロビン量の変化について解析すると重力が変化した直後の静脈還流に差があるだけで、すべての被験者で過重力時には脳血流量は減少し低重力時には増加することが示唆された。 重力が変化した場合、静水圧の変化により頭部での脳還流圧も変化する可能性がある。しかし、脳血流量に影響を与えているのは、おそらく脳還流圧の変化よりも心拍出量の変化と思われる。なぜなら、頭部レベルでの静水圧は変化していない下半身陰圧負荷においても脳血流量は減少しているからである。これまでの報告によれば起立試験、過重力負荷、下半身陰圧負荷いずれにおいても血液が下半身にプールされることにより心拍出量の減少が生じ、低重力の場合には逆に心拍出量は増加する。 過重力負荷時には脳血流量と脳血液量ともに減少し、低重力環境では脳血流量と脳血液量ともに増加することが示された。0Gから2Gの範囲で重力が変化する場合、脳動脈で代償性反応が生じている可能性はあるものの、脳血流量はかならずしも一定に保たれないことが示唆された。 | |
| 審査要旨 | 本研究は人間が過重力および低重力環境におかれた場合の脳循環動態を解析したものである。過重力および低重力環境におかれた場合の脳循環動態は、これらの環境下での安全性を考える上で重要と考えられるが、これまで報告がほとんどない。本研究では、20歳台の健康人を被験者にして、1)電動ベッドによる受動的起立、2)遠心装置による過重力負荷、3)下半身陰圧負荷、そして4)ジェット機での弾道飛行による無重力という4つの実験系で脳循環動態の解析を試みており、下記の結果を得ている。 1.被験者を電動ベッド上で臥位におき、30秒間で60度まで頭部高位の位置にベッドを傾けた。総頚動脈血流量、中大脳動脈平均血流速度、脳組織内酸化ヘモグロビン、還元ヘモグロビン量を測定した結果、脳血流量および脳血液量ともに減少していることが示唆された。 2.被験者を半径2.4mの遠心加速装置に乗せて、頭部から足の方向に1.5Gを30分間負荷した。脳組織内酸化ヘモグロビン量と還元ヘモグロビン量を測定した結果、起立試験と同様の傾向を示し、脳血流量および脳血液量ともに減少していることが示唆された。 3.被験者の下半身を腸骨陵以下で密閉して、下半身に30mmHgの陰圧を25分間負荷した。総頚動脈血流量、中大脳動脈平均血流速度、脳組織内酸化ヘモグロビン、還元ヘモグロビン量を測定した結果、動脈系での血管拡張が生じているものの脳血流量は減少していることが示唆された。 4.被験者をジェット機に乗せ、約25秒間の無重力状態を体験させた。中大脳動脈平均血流速度、脳組織内酸化ヘモグロビン、還元ヘモグロビン量を測定した結果、脳血流量および脳血液量ともに増加していることが示唆された。 以上より、本論文は0Gから2Gの範囲で重力が変化する場合に、脳血流量は決して一定に保たれない、むしろ重力負荷に依存して変化していることを明らかにした。さらに下半身陰圧負荷とそれ以外の実験系の結果との比較から、血液シフトに伴う循環血液量の増減によって生じる心拍出量の変化が重力変化時の脳循環動態に最も影響を与えうる要素であることを示した。本研究はこれまでほとんど知られていなかった重力変化時のヒトにおける脳循環動態を非侵襲的にしかも連続的な方法で明らかにしたという点で、宇宙航空医学および脳循環代謝の分野で重要な貢献をなすと考えられ、学位の授与に値するものと考えられる。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/53974 |
 を用いて収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍を1心拍ごとに測定した。さらに中大脳動脈血流速度を連続で、脳組織内酸化および還元ヘモグロビン量を2秒ごとに測定した。
を用いて収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍を1心拍ごとに測定した。さらに中大脳動脈血流速度を連続で、脳組織内酸化および還元ヘモグロビン量を2秒ごとに測定した。