学位論文要旨
| No | 212995 | |
| 著者(漢字) | 大林,正博 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | オオバヤシ,マサヒロ | |
| 標題(和) | 神経性食欲不振症の入院行動療法 : 退院6カ月後における不食型と大食型の体重および社会適応度の比較 | |
| 標題(洋) | ||
| 報告番号 | 212995 | |
| 報告番号 | 乙12995 | |
| 学位授与日 | 1996.09.11 | |
| 学位種別 | 論文博士 | |
| 学位種類 | 博士(医学) | |
| 学位記番号 | 第12995号 | |
| 研究科 | ||
| 専攻 | ||
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 神経性食欲不振症(Anorexia nervosa以下,AN)の研究において,過食を伴うAN(大食型)と,過食を伴わないAN(不食型)を比較検討した報告は少なくない。しかし,治療反応という視点からの報告は散見される程度である。ところで,行動療法的アプローチはANの体重増加を図る手段として広く用いられているが,この治療技法に対して疑問や批判が提示されることも少なくない。それは,(1)体重増加後の維持や再発,(2)食行動,社会適応などの体重以外の治療反応,(3)体重増加を図ることの治療的意義や予後との関係,(4)下位分類による治療反応の差異など,に関するものである。 不食型と大食型に対して体重増加目的の入院行動療法という一定の治療法を施行し,入院中の反応や退院6カ月後の体重,社会適応度,食行動,月経などを比較検討することで,この二つの病態の治療的関与による反応や予後の違いを考察することに加え,行動療法に対する批判や問題点を検討することを目的とした。 対象は体重増加を目的とした入院行動療法を施行したAN72例で,次の二群に分類し,6カ月間経過観察を行った。(1)過食嘔吐の既往がないもの(不食型)43例,(2)過食嘔吐の既往があり,入院時も過食嘔吐が著しいもの(大食型)29例。この72例のうち退院6カ月以前での中断,終了例を除いた不食型38例,大食型26例の合計64例を統計的解析の対象とした。 入院時体重,発症年齢,入院時年齢,入院時社会適応度などにおいては二群間で有意差が認められなかった。また,入院期間,退院時体重,目標達成度などにおいても有意差が認められたものはなく,行動療法施行による二群間の入院中の反応の差もなかったと考えられた。 退院6カ月後においては体重,体重変化,社会適応度において有意差が認められた。退院6カ月後の体重は退院時に比べ不食型では平均1.28kg(標準体重比.024)の増加,大食型では平均3.82kg(同.072)の減少であった。また退院6カ月後の社会適応度などにおいても不食型の方が良好であった。 退院6カ月後の体重変化を従属変数として,病前最大体重,入院時体重,発症年齢,入院時年齢,入院時社会適応度,入院期間,退院時体重,目標達成度および不食型か大食型かの病形分類などを独立変数として重回帰分析をおこなった。これらの結果から不食型であること,入院時年齢が低いこと,などが体重増加に貢献していると考えられた。このことや退院6カ月後の結果などから,体重増加目的の行動療法に対してなされる「体重は増加しても,維持には問題がある」という指摘は大食型には当てはまるが,不食型においては当てはまらないと考えられた。 入院時社会適応度と入院時体重の間では二群とも有意な相関関係がなかったが,退院6カ月後との比較では不食型においては社会適応度が好転しているものほど体重の増加がみられた。体重増加を図ることの治療的意義についての疑問は未だ明確な結論をみないが,不食型,大食型を区別して検討する必要があると考えられた。 不食型においては,体重増加という当初の治療目的を果たしていると考えられた。また,体重増加に伴って学校や職場への積極的な参加がみられることが窺われた。このため,不食型は体重増加目的の行動療法の良い適応であると考えられた。一方,大食型においては退院後は体重が減少し,また社会適応度も改善せず,さらに体重(および体重増加)と社会適応度も相関しないことから,この技法は不食型ほどには有効に機能していないと考えられ,大食型に対しては体重増加以外の目標設定,治療技法の工夫が必要であると思われた。 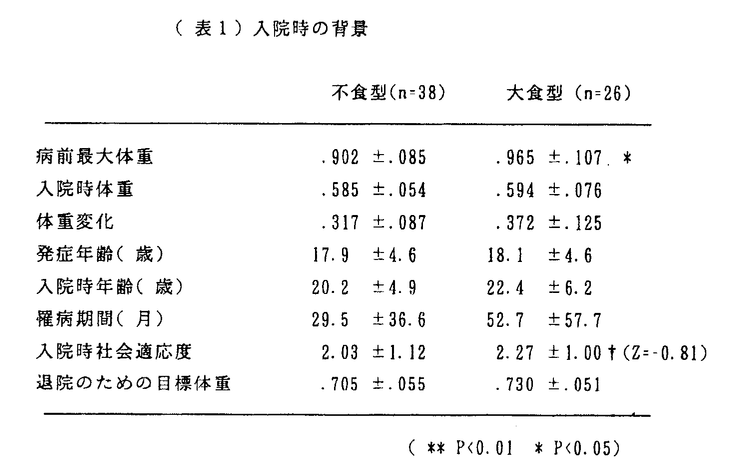 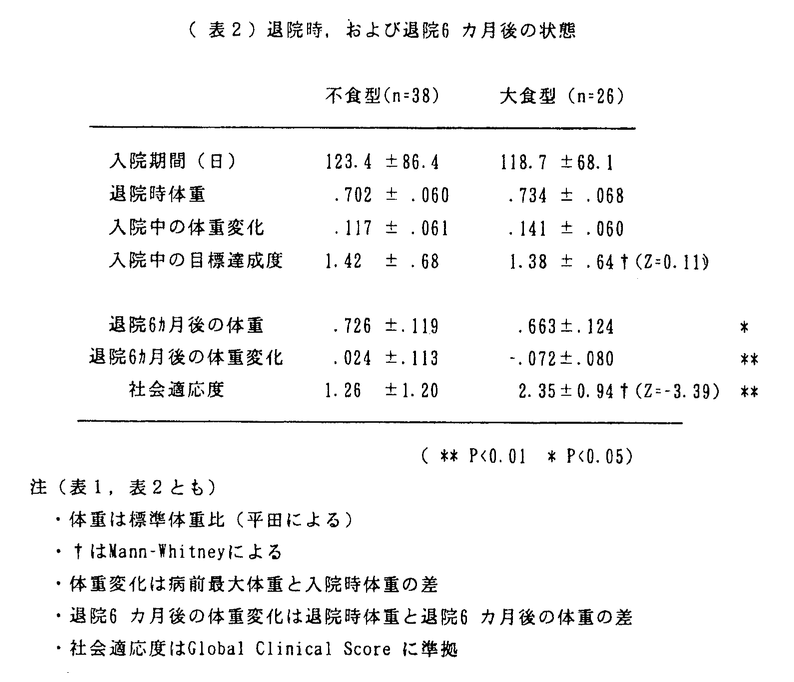 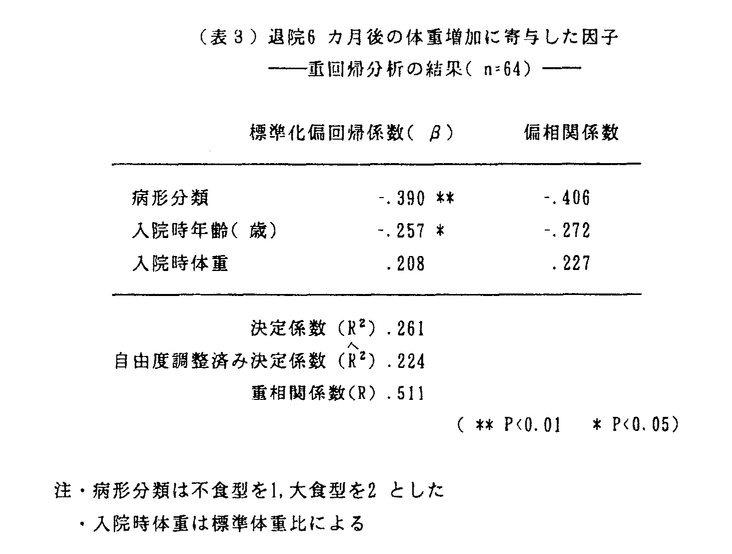 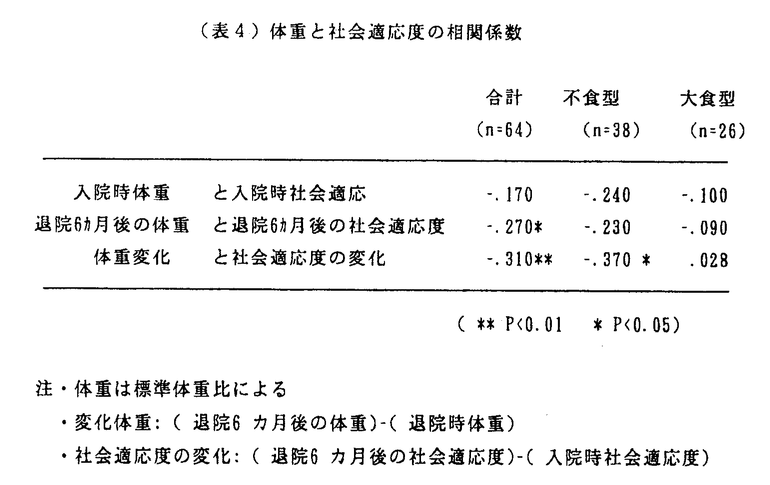 | |
| 審査要旨 | 本研究は神経性食欲不振症(Anorexia nervosa以下,AN)において,不食型と大食型を治療反応という視点から比較検討した報告が稀であること,および行動療法的アプローチはANの体重増加を図る治療手段として広く用いられているが,疑問や批判が提示されることが少なくないことを踏まえ,不食型と大食型の二群に対して体重増加目的の入院行動療法という一定の治療法を施行し,入院中の反応や退院6カ月後の体重,社会適応度,食行動,月経などを比較検討することで,この二つの病態の治療的関与による反応や予後の違いを考察することに加え,行動療法に対する批判や問題点を検討したものであり,その結果,下記の知見を得ている。 i行動療法施行による二群間での入院中の反応の差はなかった。 ii退院6カ月後の体重は退院時に比べ不食型では増加したが,大食型では減少した。 また退院6カ月後の社会適応度などにおいても不食型の方が良好であった。iii退院6カ月後の体重変化を従属変数とし,病前最大体重,入院時体重,発症年齢,入院時年齢,入院時社会適応度,入院期間,退院時体重,目標達成度および不食型か大食型かの病形分類などを独立変数として重回帰分析をおこなった結果からは不食型であること,入院時年齢が低いこと,などが体重増加に貢献していると考えられた。 iv入院時社会適応度と入院時体重の間には二群とも有意な相関関係はなかった。一方,入院時と退院6カ月後との比較では不食型においては社会適応度が好転しているものほど体重の増加がみられた。 以上のことから,不食型と大食型の比較において,入院中の治療反応は変わらないが予後には差異が見られることを示し,大食型は不食型に比べて予後不良であるという,主として自然経過から得られたと思われる従来の見解を治療反応という視点から裏付けるという貢献をした。また体重増加目的の行動療法に対してなされる「体加は得られても,その後の維持には問題がある」などの従来の批判的な指摘は大には当てはまるが,不食型においては当てはまらないことを示した。さらに体重を図ることの治療的意義についても不食型と大食型に分けて検討する必要があるを示すなど,今後,体重増加目的の行動療法の研究においては不食型と大食型をして行う必要があることを指摘するとともに,行動療法に対する疑問や批判に答という貢献をなしたと考えられ,学位の授与に値するものと考えられる。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/53975 |