パルメニデスは、「探究」の言語としての、〈こころ〉言語の確立者であった。かれは〈こころ〉言語の典型である詩、とくに叙事詩(主としてホメロス)の言語を、徹底して改鋳し、根拠を探究するための言語を創出した。 それはたんに哲学探究のみではなく、あらゆる論理・理論・科学・思想言語の根本性格を決定し、さらには芸術・宗教のもっとも重要な契機としての〈こころ〉の機能を根底から規制して、今日までわれわれを拘束している〈こころ〉の言語機構の原型を提示した、と言っていい。つまりわれわれがなんらか理論めいた思考・発言をするとき、〈こころ〉に湧き浮かぶなにかを表現しようとする際には、不知不識のうちにいつでもパルメニデスの呪縛にかかっている、とも言えるわけである。 どんなに科学が瞠目の進歩を示し、思想・宗教が鬼面人を驚かす新奇な構築を見せても、結局はそれらすべてがパルメニデスの創建した〈こころ〉言語の掌上で踊っていることを看破すれば、科学の変貌、思想・宗教の閉塞に対するわれわれの対処方式にも、また別の方途が披ける希望が生じよう。本論文は、こうした射程の中でパルメニデスを俎上に載せ、可能なかぎり周到に解剖し、かれの「探究」の到達点を明晰に分析し、〈こころ〉言語の汚染を脱して無垢な根拠を探る途を開拓しうる可能性を解明しようとした試みである。 パルメニデスの「探究」は、主語なき「ある」の可能性から、われわれのあらゆる〈こころ〉言語の究極に、それらを成立させている根拠としての「有り!」へと還帰しゆく道程を示す。しかしそれは、日常の記述言語(〈述べ〉言語)からも、伝統の詩言語からも脱出して、まったく新しい〈わたし〉〈こころ〉言語(「独り子」言語)を創出するという厳密な方法に貫かれ支えられている。 そしてこれは、かれの「探究詩」が、 (1)序曲 若き日の〈わたし〉が出遭った天門開披の体験 (2)本曲(2・1)「真理の道」(あるいは「〈有り〉の道」)(2・2)「想い込みの道」の三部構造になっている点とも相応する。 すなわち(1)「序曲」は、本曲「探究の道」が、日常世間を遠く離れて〈わたし〉独りの体験によって開かれたことを示すが、その語りはほぼ叙事詩言語の伝統に即しつつも、肝腎な点では明確に叙事詩の言語用法を改変している。 (2・1)「真理の道」における「探究」は日常言語ないし叙事詩言語とはまったく異なる自閉性をもつ論理言語によって一貫される。したがってその論理構成は〈述べ〉を基準とする通常の論理学言語とは別種独特のかたちをとる。 (2・2)一転して「思い込みの道」は、ほとんど日常言語およびこれに連なる叙事詩言語の地平で語られる(「真理」の立場から言えば「騙られる」)。 したがってパルメニデスに出会うためには、たんにかれの詩をわれわれの〈述べ〉言葉で解説するだけではなく、これら言語機構の構成と段階をまず了解しておかなければならない。 次に、これら各局面における本論の主な主張点を挙げておく(以下の数字はDiels-Kranzによる真正断片番号とその行数「.以下」である)。 (1)序曲にあっては、まず(i)従来のすべての研究者たちが解読不可能であった 「アーテーによって]を叙事詩とはまったく違う探究方式の開示として写本通りに読み切った。 「アーテーによって]を叙事詩とはまったく違う探究方式の開示として写本通りに読み切った。 (ii)「輝く澄気の門扉」(1.13)を、自然界でもっとも光輝に満ちたアイテールが、それ以上の光燿に満ちる真理を遮蔽していると理解した。 (iii)第1断片の最後の2行(1.31 32)を、「想い込みの道」への言及ではなく、女神の開示する「真理」もまた、あくまで若者たる〈わたし〉の〈こころ〉に開かれる〈立ち現われ〉以外ではないと指摘して、〈わたし〉〈こころ〉言語を超える根拠への途を示唆するものと解読した。 (2・1)「真理の道」は、探究する「思い」が(主語ともならぬながら)なにか「ある」とする点を手掛かりとして、終にそのなにかが「思い」の根拠たる「有り」であったことに到達する帰郷(根拠への回帰)の旅路であった。 (i)(〈わたし〉が天門開披の体験で出会ったなにかを)「ある」とするのか、「ない」とするのか、の二者択一の方法を基礎定立とする(2)。 (ii)そして「思い」の中での「ある」、つまり「ある」と言い、思いうる可能性から出発し(3;6.1)。「ない」ことはありえないとの不可能性を媒介として、「ある」の必然性を確立する(6.1 2)。 (iii)それ以外の「〈ない〉とする道」(真理拒否の虚無主義)、「〈あり〉かつ〈ない〉とする道」(日常経験主義)は断乎斥けられ(6.3 9,7.1 5)、ただ「言葉によることわけ の道」のみが「探究の道」とされる(7.5 6)。 の道」のみが「探究の道」とされる(7.5 6)。 (iv)「真理の道」はいまここに〈わたし〉〈こころ〉に生まれ披ける、〈わたし〉独りだけの全体(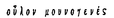 8.4これはほかならぬ天門開披の体験に呼応する)の追究であり、この追究は〈わたし〉という自閉された言語空間(「独り子言語」)における独特の論理立てによって遂行される。 8.4これはほかならぬ天門開披の体験に呼応する)の追究であり、この追究は〈わたし〉という自閉された言語空間(「独り子言語」)における独特の論理立てによって遂行される。 (v)この新生の〈こころ〉言語空間は、一切の生成消滅地平とかかわりなく(不生不滅8.3,5 6,6 21)、大いなる縛り(自閉性の成立)によって不変不揺な自己同一を保つ完全体となる(8.22 33)。 (vi)かくして「あると思われる」から出発した「探究の道」は頂点に達し、探究の目標であった「有り」が、実は探究する「思い」を成立させていた根拠であったことが判明する(「思いの中のあり」から「有りの中の思い」へ逆転の明示8.34 36)。 (vii)しかもそこでは〈こころ〉の内面地平を枠づけるかに想われがちな「時間」 も排除され、「時間」にとらわれるかぎり、そこには真理に適う「思い」はない、と断言される(時間座標に依る想いの排拒)。「時間」に対して、いまここなる「有り」の「思い」を(「独り子なる全体」として)成立させるのは「運命」 も排除され、「時間」にとらわれるかぎり、そこには真理に適う「思い」はない、と断言される(時間座標に依る想いの排拒)。「時間」に対して、いまここなる「有り」の「思い」を(「独り子なる全体」として)成立させるのは「運命」 であることが明言される(8.36 38)。 であることが明言される(8.36 38)。 かく読むことによって従来の解釈者たちには不可解であった8.36のシムプリキウス(アカデメイア版)写本 がその通りに読めることとなった。 がその通りに読めることとなった。 (viii)最後に〈わたし〉〈こころ〉言語の縮重によって凝結する「有り」に対応する「真球」モデルが、生滅の事実地平と対照しつつ提示され、しかも両者がそれぞれの言語機能(縛りと緩めcf.8.14)に応ずるモデルでありつつ、事実地平についての語り(実は騙り)がなおも「真球」モデルに重ね書きするものとなることが示唆され、「想い込みの道」の位置づけが準備される(8.38 49)。(2・2)「想い込みの道」は、いわばかの「真球」モデルに重ね書きされた自然宇宙像モデルの提出である。しかし「真理の道」が明晰な一義性を保つ言語(述語)だけによって披かれたのと対照して、ここでは道の展開は、ものを相互に対立し分断された事実として「名づけ」措定する言語により、しかもすべての言葉は両義性ないし多義性を帯びて、一義な明確性を欠く(8.53 55)、つまりはそこでの語りは騙りであることが明言されている(8.52,61)。 「真理の道」に比べて「想い込みの道」の断片資料の保存率は極めて低い。そのため宇宙の全貌を描く場面ではアエティオス資料からの援助は不可欠であるが、当のアエティオス所伝が混乱を極めており、真正断片の復元は困難である。ここでは可能なかぎりの資料を使って球型の天空にアイテールの輪が(おそらく天の川として)襷掛けになっている宇宙モデルを再構成してみた。 (3)従来その所属と位置が問題となってきた断片4および5は、全詩の締めくくりとして断片19の後におくことにした。 |