| 内容要旨 | | 1995年1月17日の兵庫県南部地震以来、"活断層"という言葉とともに地震予知・地震防災への関心が世間全般に高まっている。日本の活断層研究は世界でもトップレベルにあるが、150〜250年という地震の繰り返し間隔をもつカリフォルニア州サンアンドレアス断層などと比べると、日本の活断層は数千年に1回の活動といわれており、その地震危険度評価には困難を伴う。しかし、空中写真判読、掘削調査などを通じて日本の個々の活断層の位置や活動史に関するデータは着々と蓄積されており、これらを用いて内陸直下型地震の長期危険度評価に関する有意義な結果を得ることが期待された。 活断層データを用いた日本の地震危険度については、過去にもいくつかの研究がおこなわれている。しかし、それらは地震の発生がランダムに起こるという仮定のもとで計算されており、活断層の活動履歴が考慮されていない。また、活断層系のセグメンテーション問題とそれに関連する地震の規模予測についての研究も十分おこなわれていない。そこで、本研究では日本全土について、上に述べた問題を考慮したより実際的な内陸地震の危険度評価を目指した。さらに、内陸地震の発生によって、その周辺の活断層の地震危険度がどのくらいの割合で変化するのかをモデルをもちいて考察することを試みた。 まず、(1)個々の活断層の再来周期には規則性があるのか、それともランダムなのか、(2)地震が起こるときに活断層系は常に全長にわたって破壊するのか、の2点について、1つの活断層系のなかで行われた複数のトレンチ調査の結果をもちいて考察した。その結果、再来間隔には正確な周期性は見られないが、まったくランダムでもないこと、内陸地震が起こるとき常に活断層系の全長に破壊がおよぶわけではないこと、が示された。 次に、3回以上の古地震の履歴が得られている活断層について、個々の再来間隔とその平均の比をとって分布を調べた。値は0.5から1.7の間に分布した。古地震年代の推定誤差については、Monte-Carloシュミレーションをもちいて計算にはばをもたせ、さらにワイブル関数を用いてその分布を統計的に近似した(図1)。 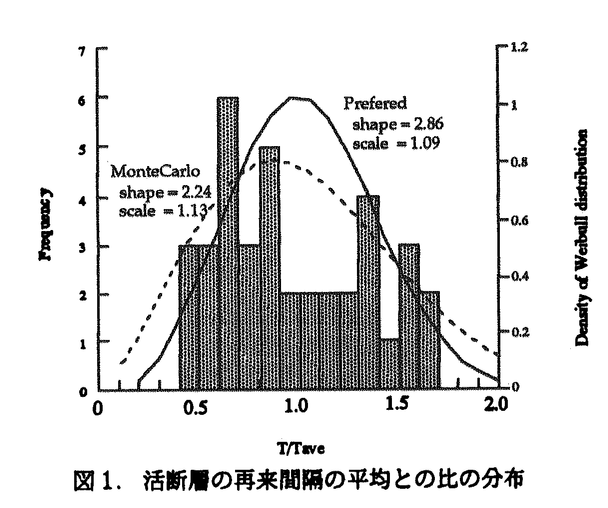 図1.活断層の再来間隔の平均との比の分布 図1.活断層の再来間隔の平均との比の分布 得られたワイブル分布関数を用いて、最後に地震を起こした年代のわかっている丹那断層(1930年、北伊豆地震)と糸魚川-静岡構造線に属する午伏寺断層(841年、信濃地震)について、各々の活断層が21世紀中に大地震を引き起こす確率を、活動履歴を考慮した条件付き確率として求めた。この値と、これまでの研究で広くもちいられてきた、活断層はランダムに活動する、という仮定からもとめられた確率と比較した。その結果、条件付き確率のほうが活断層の実際的な危険度評価に有効であることが示された。 次に、同様の手法を適用して日本全国の長期地震危険度評価マップを作成することを試みた。まず日本列島の活断層を、その分布状況から350余りの活断層系にまとめた。その際、30km以上の長さを持つ活断層系については、全長が同時に破壊するというシナリオの他に、地図上でのトレースに表現される断層ステップや断層ジョグで区分された約20kmの複数のセグメントが個別に破壊するというシナリオも設定した。発生しうる地震の規模は、地震断層の経験則をもちいて断層の長さから計算した。 上記の2つのシナリオについて、変位速度の推定誤差も考慮して、過去400年間の歴史地震活動と比較した。その結果、活断層系の長さと変位速度について、セグメントに区分して平均変位速度を与えたときに、歴史地震の規模と頻度の関係をよく説明することが示された。 時間軸を考慮した条件付き確率を求めるのに不可欠な活断層の最終活動時期については、歴史地震を解析した研究の結果をまとめて、歴史時代の活動履歴をできうるかぎり求めた。最後の活動時期が不明な活断層については、日本の歴史地震記録が約1000年の長さをもつことから、その経過時間を1000年と仮定した。この仮定は、個々の活断層に小さな危険度評価をあたえるものである。 こうして得られたデータと仮定をもとに、21世紀中に0.2g以上の最大水平加速度を被る確率を計算した。さらに、表層地質による地震動の増幅効果も考慮して、同期間に10%の確率で被ると予想される最大水平加速度を計算して図示した(図2)。  図2.21世紀中に10%の確率で被ると予想される最大水平加速度 図2.21世紀中に10%の確率で被ると予想される最大水平加速度 それによると、大きな変位速度もちかつ最終地震からの経過時間が長いと考えられる糸魚川-静岡構造線や伊那谷断層、中央構造線などについて大きな確率と最大水平加速度が予想された。一方、過去数百年のうちに大地震を起こしたことのある活断層については、確率が小さく計算され、相対的な危険度は小さいと考えられた。  図2(続き).21世紀中に10%の確率で被ると予想される最大水平加速度 図2(続き).21世紀中に10%の確率で被ると予想される最大水平加速度 こうして作成される日本の地震危険度マップは、地震学、テクトニクスなどの理学的分野だけでなく、ビルや発電所の耐震設計といった工学的な問題や、保険料率の作成といった社会的な問題にも有効な指針を与えると考えられる。 ここまでの解析では、活断層間の相互作用を考慮せず、個々の断層は互いに独立に活動するものと仮定した。本研究では最後に、内陸大地震が周辺の活断層の危険度をどのくらいの割合で変化させるのかを調べるために、大地震によって引き起こされる個々の活断層の応力変化と、活断層が活動する際に予想される応力効果量および活断層の平均再来間隔を、日本で過去100年間におこった内陸地震について計算して比較した。 その結果、震源断層の極近傍(約20km)に位置する活断層を除けば、静的応力変化の絶対量は1bar程度であり、活断層の応力効果量および平均再来間隔の約1%相当にすぎない。しかし、大地震後の実際の余震活動と、モデル計算による応力変化によって地震が起こりやすくなったと予想される地域との間に相関があることや、また大地震の後、周辺地域に生じた中規模地震のほとんどの例で地震を起こりやすくさせる応力変化が生じていた例が明らかとされた。これは、大地震にともなう応力変化が、地震危険度の予測に影響をおよぼす効果があることを示している。今後、活断層のパラメータについてのさらに詳細な研究が必要である。 ここで得られた手法および結果は日本の内陸直下型地震の長期地震危険度評価に関する一つの試みであり、さらに詳しい古地震調査データや地球物理学データの蓄積によって計算のパラメータに改良が加えられ、より実際的な結果を得ることが可能になると考えられる。 |
| 審査要旨 | | 本論文では,日本列島の陸域で発生するいわゆる「内陸直下型地震」の発生確率を,地形学的・地質学的方法で求めた活断層の過去の活動履歴等に関するデータに基づいて推定している.活断層データを用いた日本の地震危険度については,過去にもいくつかの研究事例がある.しかし,それらは地震の発生がランダムに起こるという仮定のもとで計算されており,活断層の活動履歴が考慮されていなかった.また,活断層系のセグメンテーション問題とそれに関連する地震の規模予測についての検討も十分おこなわれなかった.さらに,断層間の相互作用(個々の内陸地震の発生によって,その周辺の活断層の地震発生危険度がどのくらいの割合で変化するか)についても考慮されていなかった.本論文では,これらの問題を考慮し,より実際的な内陸地震の危険度評価を試みている. 本論文の主要部・(第1章General Introductionと最後の第5章General Conclusionを除く)は,3部から構成される.第1部では先ず,(1)個々の活断層の再来周期には規則性があるのか,それともランダムなのか,(2)地震が起こるときに活断層系は常に全長にわたって破壊するのか,の2点について,活断層のトレンチ調査のデータを基に考察している.その結果,断層から発生する地震の再来間隔は,ランダムではなくて,ある種の周期性があること,および一つの内陸地震に伴って常に活断層系の全長に破壊がおよぶわけではないこと,の2点が明らかにされた.次に,活断層から発生した古地震の再来間隔(平均再来間隔で正規化したもの)の分布を調べ,正規化した再来間隔の分布がワイブル関数を用いて統計的に近似できることが明らかにされた. 第2部では,上記の手法を適用して日本全国の長期地震危険度評価マップを作成することを試みている.その際,30km以上の長さを持つ活断層系については,全長が同時に破壊するというシナリオの他に,複数のセグメントが個別に破壊するというシナリオを設定した.この2つのシナリオのどちらが有効かを,過去400年間の歴史地震活動データと比較する事により検討した.その結果,セグメント区分のシナリオが,歴史地震の規模と頻度の関係をよりよく説明することが示された.さらに,条件付き地震発生確率を求めるのに不可欠な活断層の最終活動時期については,活断層のトレンチ調査データと歴史地震データから求めた.最終活動時期が不明な場合は,その経過時間を1000年と仮定した.こうして得られたデータと仮定をもとに,21世紀中に0.2g以上の最大水平加速度を被る確率を計算した.さらに,表層地質による地震動の増幅効果を考慮して,同期間に10%の確率で起こると予想される最大水平加速度を計算して図示した.それによると,最近の地質時代における平均変位速度が大きくかつ最終地震からの経過時間が長い糸魚川・静岡構造線,伊那谷断層,中央構造線などについて,強振動発生の確率が高くかつ予想される最大水平加速度も大きいことが明らかにされた. 以上の解析では,個々の断層は互いに独立に活動するものと仮定し,断層間の相互作用を考慮していない.本論文の第3部では,内陸で発生する大地震が,周辺の活断層の地震発生確率をどのくらいの割合で変化させるかを検討している.大地震によって周辺の活断層上で引き起こされる静的応力変化の値は,震源の極近傍(約20km以内)に位置する活断層を除けば,1bar程度である.この値は,その活断層が動いたときに生じる応力降下量の約1%であり,従ってこの断層の活動間隔を1%程度変化させるにすぎない.しかし,モデル計算から求めた過去の大地震に伴う応力変化パターンと,実際の余震活動のパターンとの間に相関が認められる.また大地震の後,周辺地域で起こった中規模地震のほとんどについて,地震を起こりやすくさせる応力変化が生じていたことが明らかになった.これらの結果から,大地震にともなう応力変化が,周辺の活断層の地震発生確率に有意な影響をおよぼす可能性が指摘された. 以上のように,本論文は,過去の研究事例では考慮されなかった問題点を解決した上で,より実際的な内陸地震の危険度評価を試みた点で画期的である.本論文で提示された日本の地震危険度マップは,テクトニクスや地震学などの理学的分野だけでなく,ビルや発電所の耐震設計といった工学的な問題や,保険料率の算出といった社会的な問題にも有効な指針を与えると考えられる.従って,博士(理学)を授与できると認める. |