食品のおいしさには味、香り、食感、外観など、さまざまな要素が関わっているが、食生活の向上に伴なって、"こく"や"複雑味"といった言葉で表現される風味を併せもつ調味料が求められるようになってきた。従来から食品の呈味に関する研究は多いが、これらは総じて甘味やうま味などの基本味に関するもので、風味についての研究は少ない。なかでも食品中のペプチドの風味に関する研究はまれである。グルタチオン(GSH)は動植物中に広く分布するトリペプチドであるが、その呈味性を含めた食品化学的性質についてはほとんど注目されていなかった。しかし近年、加熱食品香気の前駆物質としてGSHの研究が行われるようになり、その風味への関与についても興味が持たれるが、現在のところ全く知見がない。 本研究はこのような背景のもとに、GSHの風味特性を明らかにすることを目的とし、まずGSH単独の味および他の呈味物質と共存した場合の呈味効果を調べた。次いで、GSHを含有するいくつかの食品素材を対象に、その風味に対するGSHの関与の有無を調べるとともに、加熱時のGSHの安定性を明らかにした。最後に、これらの研究成果を生かしたGSH含有の新製品の開発をめざした。以下に得られた研究成果の概要を述べる。 1.GSHの風味特性と食品中の含有量 GSHの風味特性を、他の物質との相互作用の観点から調べた。はじめに、純水中、中性下でGSHの閾値を調べたところ40mg/100mlであった。そこでこの閾値を上回る200mg/100ml濃度での呈味を官能評価したところ、GSHは基本味(甘味、塩味、酸味、苦味、うま味)を呈さなかった。次に苦味を除いた4種の基本味溶液に閾値濃度のGSHを添加したところ、GSHはこれら基本味の強度に影響を与えないことが明らかとなった。続いて、うま味物質が他の食品成分と相互作用をひき起こし、食品の風味を増強する特性があることを踏まえ、うま味溶液中でのGSHの効果を調べた。その結果GSHの閾値は、グルタミン酸1ナトリウムとイノシン酸2ナトリウムから成るうま味溶液中では10mg/100mlと1/4に低下した。次いで、うま味溶液に20mg/100mlのGSHを添加してパネル試験を行ったところ、GSHはうま味は強めないが、"あつみ"、"ひろがり"、"持続性"という官能評価用語で表現される風味を発現した。この風味を本研究ではGSHの"こく味"と定義した。一方、GSHの酸化型であるGSSGの効果をGSHと比較したところ、弱いながらもやはりうま味溶液中で"こく味"を発現した。 次いで、畜肉類、生鮮魚介類、加工食品を対象に、GSHおよびGSSGをHPLC法で定量した。その結果、GSHは牛肉、豚肉、鶏肉で多く、13〜38mg/100gであった。またワインでも3.0〜38mg/100g濃度で検出されたが、魚肉での含有量は0.2〜9.2mg/100gと、低いレベルにあった。一方、貝類ではホタテガイ閉殻筋で9.6〜29mg/100gと、最も含有量が高かった。供試魚介中では、概してGSSGはGSHに比べて少なかったが、メバチとカツオではGSSGの方が多かった。 2.食品中のGSHの風味に及ぼす影響 いくつかの食品を取り上げ、風味とGSHの関係を検討した。まず、牛肉抽出液の分析値を基にGSHを除いて合成エキスを再構成し、GSHを分析値濃度(20mg/100ml)で添加して官能評価を行った。その結果、GSHは基本味には影響しないが、"こく味"および"牛肉らしさ"を有意に強めた。これらの結果から、GSHが牛肉の風味を構成する成分の一つであると考えられた。 さらに、含硫成分を著量に含むことで知られるニンニクを他の食品に加えた際に強められる風味、すなわち"あつみ"、"ひろがり"、"持続性"を、動物性食品の場合と同様にニンニクの"こく味"と定義し、GSHを含めた原因成分の探索を行った。ニンニク抽出物、分画して得たアミノ酸およびペプチド画分は、カレーおよび中華スープ、さらにはうま味溶液において"こく味"を発現した。ニンニク抽出物を、各種イオン交換クロマトグラフィーに付したところ、GSHをはじめとして、ニンニクに特徴的な成分とされるS-allylcysteine sulfoxide(alliin)、S-methylcysteine sulfoxide、 -glutamyl-S-allylcysteine、 -glutamyl-S-allylcysteine、 -glutamyl-S-allyl-cysteine sulfoxideが検出された。これらの成分を単独にスープやうま味溶液に加えたところ、GSHと同様に"こく味"を発現した。産地、品種別24試料のニンニクにつき含硫成分の定量を行った結果、alliinは平均2550mg/100gで、GSHは17mg/100gであった。各成分の"こく味"の強さの比較と含有量の差から、ニンニクの"こく味"の主体はalliinなどのGSH以外の含硫成分であると考えられた。 -glutamyl-S-allyl-cysteine sulfoxideが検出された。これらの成分を単独にスープやうま味溶液に加えたところ、GSHと同様に"こく味"を発現した。産地、品種別24試料のニンニクにつき含硫成分の定量を行った結果、alliinは平均2550mg/100gで、GSHは17mg/100gであった。各成分の"こく味"の強さの比較と含有量の差から、ニンニクの"こく味"の主体はalliinなどのGSH以外の含硫成分であると考えられた。 さらに、ニンニクと同じAllium属植物であるタマネギについても同様の検討を加えた。その結果、タマネギの特徴的成分であるS-propenylcysteine sulfoxide(PeCSO)、 -glutamyl-S-propenylcysteine sulfoxide( -glutamyl-S-propenylcysteine sulfoxide( -Glu-PeCSO)が"こく味"に関与することを確認した。また、含硫成分の定量結果から、ニンニクの場合と同様に、タマネギにおいてもGSHの"こく味"への寄与は小さいと考えられた。 -Glu-PeCSO)が"こく味"に関与することを確認した。また、含硫成分の定量結果から、ニンニクの場合と同様に、タマネギにおいてもGSHの"こく味"への寄与は小さいと考えられた。 次いで、GSH含有量が高かったホタテガイ閉殻筋を取り上げ、GSHの風味に果たす役割を調べた。ホタテガイの味を有するGSHを除いた合成エキスに、GSHを分析値濃度の29mg/100mlで添加し,官能評価した。その結果、GSHは合成エキスに甘味、うま味とともに"こく味"を有意に付与した。これらの結果からGSHはホタテガイの風味を構成する成分であると断定した。 3.新規GSH含有調味料の開発 GSHを添加して風味を増強した調味料を開発する目的で、まずGSHの加熱安定性を調べた。水溶液中、GSHを98℃で5時間加熱したところ3種の主要な化合物が生成した。その一つはGSSGであった。また、2-pyrrolidone-5-carboxylic acid(PCA)も生成したが、これはGSHの -glutamyl基が離脱、環状化したものと推定された。さらにcyclo cysteinylglycine(cyclo Cys-Gly)disulfideもGSHの主要分解物であることが判明した。このdiketopiperadineは、GSHのCys-Gly部分が環状化して生成したものと推定された。 -glutamyl基が離脱、環状化したものと推定された。さらにcyclo cysteinylglycine(cyclo Cys-Gly)disulfideもGSHの主要分解物であることが判明した。このdiketopiperadineは、GSHのCys-Gly部分が環状化して生成したものと推定された。 次いで、80〜98℃、種々のpH条件下でのGSHの反応様式を調べた。その結果、GSHは中性下では主にGSSG、PCAおよびcyclo Cys-Gly disulfideに変化し、また酸性下ではPCAとcyclo Cys-Gly disulfideに分解することが判明した。反応速度の解析から、GSHは2時間以内の通常の高温調理下では、かなりの量が残存しているものと推定された。しかしながら、3時間以上煮熟するような場合は、大きく減少、消失していくことが予想された。 続いて、各種食品にGSHを添加した場合の効果を調べたところ、予測通りGSHは畜肉を使用した食品において"こく味"や"畜肉らしさ"を強め、嗜好性を高めた。また、鰹だしに添加した場合においても"こく味"を付与した。これらの食品でのGSHの有効濃度は概して10mg/100g以上であったが、ハンバーグやシュウマイでは3mg/100gで有効であった。 GSH単独では食品添加物としての使用が認められていないため、実用にはGSHを多く含む天然エキスを利用する方策が考えられる。そこで、GSHの回収率を高めた酵母エキスの使用を検討した。まず、既報の知見に基づいてGSH濃度を高めた酵母を培養し、水抽出によりGSHを市販エキスの約20倍多く含む試験用酵母エキス(GSH-YE)を調製した。次に、GSH標品を対照としつつ、GSH-YEの添加効果を調べたところ、各種食品にGSH標品と同様の"こく味"を付与することを認めた。 最後に、GSHの機能を生かした食品として、風味の優れただし醤油の製造を検討した。鰹節と醤油を原料として、だし醤油の製造工程中でGSH-YEを添加した結果、だし醤油の"こく味"および"鰹だしらしさ"が強められることが確認できた。この成果をもとに開発された新製品は,現在市場で高い評価を受けている。 以上、本研究から下記の表に示すように、GSHは中性条件下で基本味を呈しないが、うま味物質との共存下で"こく味"を発現することや、畜肉やホタテガイの風味に関与していることが明らかとなった。また、加熱安定性の検討結果と添加効果をもとに、GSH含有の風味増強効果をもつ新規の調味料を開発した。 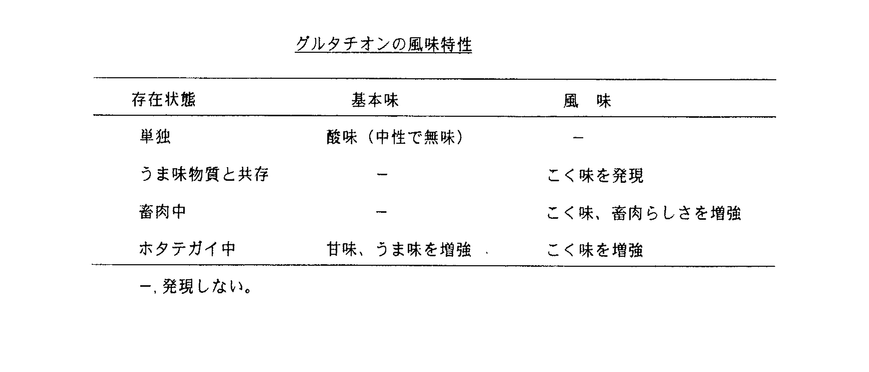 グルタチオンの風味特性 グルタチオンの風味特性 |