学位論文要旨
| No | 213709 | |
| 著者(漢字) | 本田,秀夫 | |
| 著者(英字) | Honda,Hideo | |
| 著者(カナ) | ホンダ,ヒデオ | |
| 標題(和) | 日本における小児自閉症の累積発症率および有病率 | |
| 標題(洋) | Cumulative Incidence and Prevalence of Childhood Autism in Children in Japan | |
| 報告番号 | 213709 | |
| 報告番号 | 乙13709 | |
| 学位授与日 | 1998.02.18 | |
| 学位種別 | 論文博士 | |
| 学位種類 | 博士(医学) | |
| 学位記番号 | 第13709号 | |
| 研究科 | ||
| 専攻 | ||
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 自閉症の疫学調査は,従来から多くの報告がある。しかし,疫学の最も基礎的データである頻度においてさえも一致をみるには至っていない。診断基準の不一致はしばしば指摘されるが,その他にも2つの問題点が挙げられる。 1つは,従来の頻度調査が有病率のみに限定されていることである。自閉症の病因研究のためには,発症率の正確な算出を試みる必要がある。 もう1つの問題点は,第一次スクリーニングの方法である。先行研究で用いられた方法は3つに大別される。1つめは,研究者が関係機関職員に対して質問紙法による調査を行なう方法である。第一次スクリーニングを行なうスタッフは通常は専門家ではなく,自閉症にかんする知識も様々であるため,脱落例が生じる可能性が大きい。2つめは,地域の専門機関が限られている場合に,専門機関への受診者数を有病者数とするものである。この方法では,受診が親の発意に依拠していることが多いため,専門機関を受診していない症例が登録されない。3つめの方法は,1歳6ヵ月児健康診査を活用するものである。3つの中ではもっとも洗練された方法であるものの,1歳6ヵ月での自閉症の診断の確実性についてはまだ議論があり,健診未受診者および健診の偽陰性例が脱落する可能性がある。 本研究では,自閉症の疫学研究における診断基準,発症率,および症例の登録の問題を解決する試みを行なった。まず,診断基準にはICD-10研究用診断基準(以下,「ICD-10 DCR」と略)の小児自閉症の操作的基準を用いた。次に,5歳までの累積発症率を算出することで発症時期の曖昧さの問題を解決した。さらに,スクリーニングの未受診者や偽陰性例をも掌握できるようなシステムを用いた。 1987年から1994年にかけて,横浜市総合リハビリテーションセンター(以下,「YRC」と略)の児童精神科部門は,横浜市北部に位置する港北区と緑区に居住する発達障害児に対する早期療育を行なっていた。この地域が本研究の対象地域である。1994年1月における対象地域の面積は約120km2,人口は773,339人であった。対象地域の3つの保健所はすべてYRCとの間で緊密な連携がとられている。 横浜市では乳幼児健康診査が主として保健所の集団スクリーニングの形態で行われている。小児自閉症にかんしては1歳6ヵ月児健康診査(以下,「HC-18m」と略)を第一次スクリーニングとして活用している。ここでは親からの問診および保健婦による直接の子どもの行動観察にもとづくスクリーニングが行われる。 第一次スクリーニングで把握された子どもたちは保健所によるフォローアップを受け,小児自閉症をはじめとする発達障害が疑われた場合はYRCへ紹介される。HC-18mの受診率は約90%であり,臨床的にはは十分な高さであるが,疫学調査のためには不十分である。 HC-18m未受診例や偽陰性例に対して,保健所には3歳児健診が用意されている。さらに,YRCでは地域の医療機関,児童相談所,および幼稚園や保育所と日常的に緊密な連携をとり,症例の把握に努めている。YRCには,重度の精神遅滞を伴う例から高機能例まですべての小児自閉症の症例に対して療育の場が提供されている。このような関係機関同士の緊密なネットワーク(早期発見・早期療育ネットワーク)は,疫学研究のためには第1次スクリーニングの場の内部と外部の両方にまたがって複数の"fail-safe"が装備されているような症例掌握のシステムとなる。これを「"fail-safe"システム」と呼ぶことにする。 YRCを受診した子どもたちは,まず児童精神科医の診察を受ける。ここではICD-10の「臨床記述と診断ガイドライン」(以下,「ICD-10ガイドライン」と略)に基づいて診断がなされる。初診のみでは診断を確定できない場合も多いため,初診後に医学検査,心理評価および10週間にわたる週1回の半構造化された集団プログラムによる行動観察を行ない,その後に児童精神科医が再診断するシステムをとっている。引き続いて早期療育プログラムが提供されるとともに,児童精神科医による定期的な診察が行われ,必要に応じて再診断もなされる。3歳未満の子どもが広汎性発達障害(以下,「PDD」と略)の特徴を有する場合は小児自閉症の疑診とし,3歳以降に確定診断がなされる。 本研究では,1988年に出生した子どもたちを調査の対象とした。YRCの1988生まれの症例のリストから,1度でも疑診も含め小児自閉症(ICD-10ガイドライン)と診断されたことのある症例を全例抽出した。次いでYRCの2名の児童精神科医が独立にICD-10 DCRに準拠して最終的な同定作業を行ない,小児自閉症の診断基準を満たす症例のみを同定した。 小児自閉症と同定された症例のなかから,1988年に対象地域で出生した児を選び,この人数をAとした。1988年の対象地域の出生数の総数(出生コホート)は9240名(男4719名,女4521名)であった。 小児自閉症と同定された症例のなかから,1988年に出生し1994年1月1日時点で対象地域に居住している児を選び,この人数をBとした。1994年1月1日に対象地域に居住する5歳児の人口は8537名(男4408名,女4129名)であった。 1988年に対象地域で出生し小児自閉症と診断された症例数Aは,15名(男10名,女5名)であった。 1988年に出生して1994年1月1日時点で対象地域に居住しており,小児自閉症と診断された症例数Bは,18名(男13名,女5名)であった。 AとBの間で重複していたのは14名(男10名,女4名)であった。Aの15名のうち女児1名が転出し,男児3名,女児1名が他地域から転入していた。 1988年の対象地域の出生コホートにおける小児自閉症の5歳までの累積発症率は,1万人中16.2人であった。男女別にみると,男が1万人中21.2人,女が1万人中11.1人で,男女比は1.9:1であった(Table 1)。 1994年1月1日に対象地域に居住する5歳児のなかの小児自閉症の有病率は,1万人中21.1人であった。男女別にみると,男が1万人中29.5人,女が1万人中12.1人であった。有病者数の男女比は2.6:1であり,有病率の男女比は2.4:1であった(Table 2)。 小児自閉症と診断された症例のうち,1名を除く全例に対して,5歳代で全訂版田中ビネー知能検査が施行されていた。IQ70以上を高機能自閉症として,その割合を検討した。1994年1月1日よりも前に転出した1名は,4歳代でのIQが94であったため,高機能自閉症とした。 累積発症率調査の対象15名中8名(53.3%)が高機能自閉症であった。男女別にみると,男10名中6名(60%),女5名中2名(40%)であった。 有病率調査の対象18名中9名(50%)が高機能自閉症であった。男女別にみると,男13名中7名(53.8%),女5名中2名(40%)であった(Table 3)。 5歳までの累積発症率は,5歳時点での有病率よりも小さい数値であった。これは,対象地域において転出例よりも転入例の数が上回ったためである。小児自閉症に対する公的サービスに地域較差があるとすると,適切なサービスのある地域では有病率が高くなる可能性がある。 本研究で算出された有病率は,これまでの最高値である。これには第一次スクリーニングの精度が関与していると思われる。先行研究18のなかで母集団が5万人未満のものは5つあるが,そのうち4つは有病率が10/1万を越えている。一方母集団が5万人以上の13の研究のうち,有病率が10/1万を越えているものはわずかに2つであり,有意に少なかった(p=0.044,Fisherの直接確率)。本研究の母集団は約9000人であり,加えて"fail-safe"システムを導入していることから,脱落例は最少限度であると思われる。ただし,9000人の母集団は小児自閉症の疫学調査のためには少なすぎるかもしれない。今後は異なる出生コホートについて追試を行ない安定性を検討する必要がある。 次に,第一次スクリーニングに携わるスタッフの小児自閉症にかんする知識も考慮する必要がある。Gillberg et al.(1991)は,同一地域において調査を繰り返すごとに有病率が増加したと報告しているが,その要因のひとつとして,専門家による教育によりスクリーニング・スタッフの自閉症にかんする知識が増し,その結果として検出力が向上した可能性を認めている。本研究では,早期発見・早期療育ネットワークが自閉症にかんする知識の増加に寄与している。 従来高機能自閉症は小児自閉症全体の約20%と考えられていたが、本研究では高機能自閉症の割合が予想外に高かった。ここで,仮に小児自閉症全体に対する高機能自閉症の割合が20%であるとして,本研究で同定された精神遅滞を伴う小児自閉症の症例数を基準に計算してみる。精神遅滞を伴っていたのは累積発症率調査では7名,有病率調査では9名であった。これらを全体の80%に当たると仮定すると,小児自閉症の総症例数はそれぞれ9名および11名となり,累積発症率は9.7/1万,有病率は12.9/1万となる。この数字は,母集団が5万人未満の5つの先行研究の有病率の平均値である11.9/1万に近い。つまり,本研究の累積発症率および有病率のデータが高かったことについては,"fail-safe"システムに支えられた高い検出力のあるスクリーニング方法がとられたことにより,潜在化していた高機能自閉症が同定されたことが大きな要因である。Ehlers et al.(1993)は,スウェーデンにおけるアスペルガー症候群の頻度調査を行なっており,最低でも3.6/1000という高い有病率を報告している。PDDのスペクトルのなかでも高機能自閉症とアスペルガー症候群は近接していると考えられていることから,本研究の結果は正常知能のPDDにかんする今後の研究のための貴重な資料となるものと思われる。 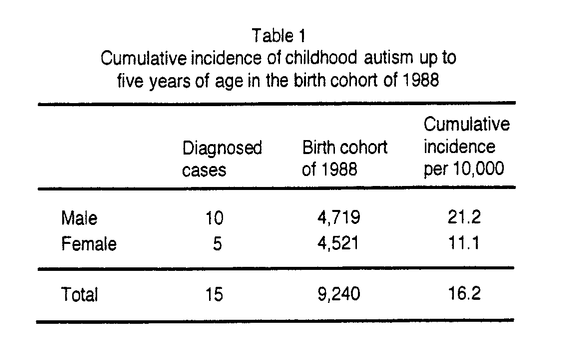 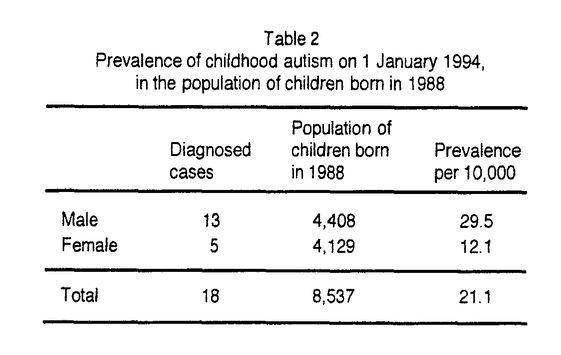 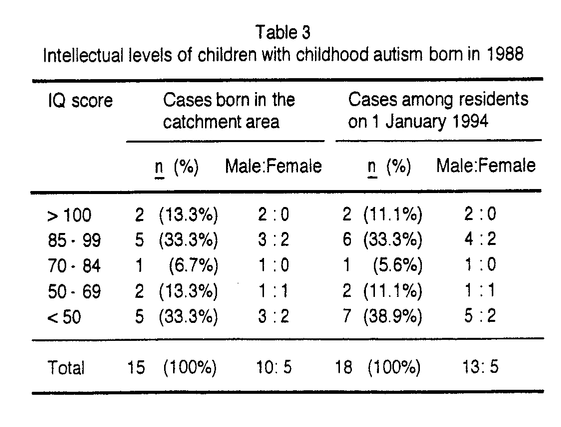 | |
| 審査要旨 | 本研究は,小児自閉症の頻度に関する研究である。現在国際的に広く普及しているICD-10研究用診断基準の小児自閉症の基準を用いたはじめての頻度調査であると同時に,従来の自閉症の疫学研究における問題点を解決する2つの方法上の新しい試みがなされている。ひとつは発症率(特定の出生コホートにおける5歳までの累積発症率)がはじめて求められたことであり,もうひとつは一次スクリーニングにおける脱落例をも確実に把握して登録できるような工夫がなされたことである。 対象地域である横浜市北部地域(人口約78万人)では,保健所で行なわれる1歳6ヵ月児健康診査を小児自閉症の一次スクリーニングとするとともに,健診の未受診例や脱落した症例があっても地域の関連機関による緊密な連携で横浜市総合リハビリテーションセンターに紹介される。このような臨床上のネットワークを,本研究では頻度調査における一次スクリーニングの<フェイル・セーフ>システムとして利用した。 このような方法上の新しい試みのもと,下記の結果を得ている。 1.1988年に対象地域で出生した子どもたちにおける5歳までの累積発症率を求めたところ,人口1万対16.2であった。男女比は1.9:1であった。 2.1988年生まれで1994年1月1日の時点で対象地域に居住する子どもたちにおける有病率を求めたところ,人口1万対21.1であった。有病者数の男女比は2.6:1であり,有病率の男女比は2.4:1であった。 3.5歳代における全訂版田中ビネー知能検査においてIQ70以上を高機能自閉症として,その割合を検討したところ,高機能自閉症が半数を占めていた。従来は高機能自閉症の割合が自閉症全体の約20%と推定されていたが,近年では高機能自閉症にたいする研究者の関心が高まり,臨床上の経験から高機能自閉症がこれまで考えられていたよりももっと多く存在するという指摘もなされていた。本研究の結果は,それを裏付けるはじめての実証データとなった。 以上、発症率をはじめて算出し,厳密な一次スクリーニングによって高機能自閉症が多数存在することを実証した本論文は,今後の小児自閉症に関する医学的研究の基礎資料として重要な意義をもつものと思われ,学位の授与に値するものと考えられる。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/50698 |