本論文は、銀河団を満たす大量の高温ガス中の重元素組成をX線で測定することにより、銀河団内の重元素の起源および銀河団中の星の生成史を探るものである。 数十〜千もの銀河が狭い領域に集まった銀河団は、さまざまな観測から、宇宙で重力的に閉じた最も大きい系であることがわかっている。この銀河団内の空間は、X線で光る高温ガス(Inter Cluster Medium:以下ICMと略す)で満たされていることが1970年代に発見された。ガスの温度は107-8K(1-10keV)、質量は銀河団中の銀河の和の数倍にも達するので、ICMは銀河団の主構成要素である。さらにICM中には太陽組成比の30%にも及ぶ鉄が存在することがX線輝線の観測から確認された。鉄を始めとする重元素は、宇宙誕生時のビッグバンでは合成されないので、これらの重元素は星の内部における核反応で合成され、それが超新星爆発や星の質量放出などによって星間・銀河間空間に放出されたと考えられる。そのため、ICM中の重元素量を詳細に測定することは、銀河団中の星の生成史や銀河形成などを含めた銀河の進化を解明するための重要な手段である。特に重元素の出すX線輝線は、光で観測される星の吸収線などより簡単な物理過程で放射されるため、ガスの物理状態などにあまり影響されずに重元素量の推定に用いることができる。また、光ではおもに星の鉄の組成しか測定できないのに対して、X線では鉄のほかに酸素、ネオン、マグネシウム、珪素、硫黄などについて、その組成比を測定することができる。鉄とこれらの重元素の比は、後述するように重元素の起源を探るうえで重要なパラメータとなる。 ICM中の重元素の起源として、おもに2つの機構が一般的に考えられている。1つは、銀河形成時に大量の重い星が起こしたII型超新星爆発(SNe II)に伴う銀河風であり、おもに酸素、珪素などの 元素が多く生成される。もう1つは、長い寿命を持つ軽い星の連星の一部が引き起こすIa型超新星爆発(SNe Ia)であり、おもに鉄を大量に放出する。よって 元素が多く生成される。もう1つは、長い寿命を持つ軽い星の連星の一部が引き起こすIa型超新星爆発(SNe Ia)であり、おもに鉄を大量に放出する。よって 元素と鉄の組成比は、重元素の起源を特定する重要なパラメータである。しかし最近までは、銀河団の全体で平均された鉄の組成しか測定できなかったため、ICM中の重元素の起源はよくわかっていなかった。 元素と鉄の組成比は、重元素の起源を特定する重要なパラメータである。しかし最近までは、銀河団の全体で平均された鉄の組成しか測定できなかったため、ICM中の重元素の起源はよくわかっていなかった。 「あすか」衛星は日本の4番目の宇宙X線観測衛星であり、これまでにない優れた分光能力、広いエネルギー帯、高い感度、さらに空間分解能を持つ。「あすか」により、鉄だけでなく 元素の組成も測定が可能となり、さらには、それらの空間分布の情報も得られるようになった。本論文では40個の銀河団について珪素、硫黄、鉄の組成比を空間分解して測定し、それをICMの温度の関数として求めることによって、重元素の起源を解明することを試みた。40個の銀河団の選定は、距離が近くて空間分解しやすいこと、重元素組成を精度よく測定できるくらい明るいこと、特異的なICM分布を持たないこと、である。さらに、できるだけいろいろなICMの温度の銀河団が含まれるように考慮した。また、観測結果を考察する便宜上、サンプルを2種類に分類した。1つは、中心に巨大楕円銀河を持ち、X線輝度がそれを中心とした鋭いピークを持つもので、cD銀河団と呼ぶ。そうでないものをnon-cD銀河団と呼ぶ。 元素の組成も測定が可能となり、さらには、それらの空間分布の情報も得られるようになった。本論文では40個の銀河団について珪素、硫黄、鉄の組成比を空間分解して測定し、それをICMの温度の関数として求めることによって、重元素の起源を解明することを試みた。40個の銀河団の選定は、距離が近くて空間分解しやすいこと、重元素組成を精度よく測定できるくらい明るいこと、特異的なICM分布を持たないこと、である。さらに、できるだけいろいろなICMの温度の銀河団が含まれるように考慮した。また、観測結果を考察する便宜上、サンプルを2種類に分類した。1つは、中心に巨大楕円銀河を持ち、X線輝度がそれを中心とした鋭いピークを持つもので、cD銀河団と呼ぶ。そうでないものをnon-cD銀河団と呼ぶ。 まずICMの全体的な特性を見るため、銀河団内で平均した温度と重元素組成を求めた。その際に、しばしばいくつかの銀河団の中心領域で観測されているような重元素の増加の影響を避けるべく中心領域を除いたスペクトルを作った。これらのスペクトルはいずれも1温度プラズマモデルでよく再現でき、結果として銀河団の平均的な温度および珪素・硫黄・鉄の重元素組成を、これまでにない精度で求めることができた。得られた重元素組成をICM温度の関数として見てみると、鉄は温度によらずほぼ0.3solarの組成比で一定であった。「ぎんが」衛星の観測から、銀河団内での平均の鉄の組成比は温度に対して負の相関をもつことが知られているが、中心を除いて得られた今回の結果は、それとは一致しない。これは、重元素分布に空間勾配があることを示唆する。また、硫黄は鉄とほぼ同じような温度依存性を示し、ほぼ0.3solarであった。いっぽう、珪素は温度に対して正に相関し、温度が1keVから4keVまで増加するにつれて0.3solarから0.6-0.7solarに増加する。その結果、図1に示すように珪素と鉄の組成比は温度に対して有意に正の相関を持つことになる。鉄のLラインの理論計算に伴う不定性や、検出器の応答関数に付随する不定性などを考慮しても、求まった結果はそれほど影響を受けなかった。また、温度と重元素組成を、銀河団の半径方向および方位角方向に分解して測定したが、上の結果に影響を与えるほどの非一様性はなかった。 以上で扱ったのは、ICM中の水素に対する各元素の相対量であるが、重元素の絶対量も重要な物理量である。そこで次に「あすか」で得られたX線輝度分布を モデルを用いて定量化し、ICMの質量を半径の関数として求め、それに重元素組成をかけることによってICM中の重元素の質量を求めた。また光学データから、銀河団中の星の総質量を求め、これをX線の結果をつき合わせることで、星に対するICM中の重元素の質量比を得た。この量は、星の単位質量に対して重元素がどれだけICMの中に残っているかを与えてくれる。もし銀河団ごとで重元素生成率が同じでありどの銀河団も重元素をすべて閉じ込めているとすると、この量はどの銀河団でも同じ値になると考えられる。得られた星に対する重元素の質量比は、低温銀河団ほど系統的に小さく、その傾向は珪素の方が顕著であった(図2)。 モデルを用いて定量化し、ICMの質量を半径の関数として求め、それに重元素組成をかけることによってICM中の重元素の質量を求めた。また光学データから、銀河団中の星の総質量を求め、これをX線の結果をつき合わせることで、星に対するICM中の重元素の質量比を得た。この量は、星の単位質量に対して重元素がどれだけICMの中に残っているかを与えてくれる。もし銀河団ごとで重元素生成率が同じでありどの銀河団も重元素をすべて閉じ込めているとすると、この量はどの銀河団でも同じ値になると考えられる。得られた星に対する重元素の質量比は、低温銀河団ほど系統的に小さく、その傾向は珪素の方が顕著であった(図2)。 銀河団ごとで重元素生成率が異なる観測的証拠や理論的根拠はないことをふまえて以上を解釈してみると、低温銀河団における星に対する重元素の質量比の減少は、低温銀河団ほど重元素の閉じ込め効率が小さいことを示唆する。これは、ICM温度が銀河団の重力ポテンシャルの深さを反映していること、銀河団よりも小さい系である楕円銀河や銀河群では重元素が系外に逃げ出していることを示唆する観測結果が最近得られていること、などからも類推される。 今回得られた高温銀河団の珪素と鉄の間の組成比は、「あすか」初期に得られたいくつかの高温銀河団の結果と一致しており、本論文では多数のさまざまな温度の高温銀河団に対して、この傾向が一般的に成り立っていることを示した。その組成比は、ICM中の重元素の多くがSNe IIによって生成されたことを支持する。さらに、低温銀河団ほど珪素に比べて鉄が増加するという事実は、鉄を大量に生成するSNe Iaが低温銀河団のICM中の重元素の生成に寄与している証拠である。このことから、低温銀河団ほどSNe II生成物が逃げ出している可能性が示唆される。一方、銀河団の規模によってSNe IaとIIの比率が変わることでも上の結果は説明できるが、理論的観測的にこうした比率の変化は積極的には支持されていない。重元素の閉じ込め効率が低温銀河団ほど小さいという可能性は、次に述べるような銀河団中の重元素生成史の一般的なシナリオとも合う。すなわち銀河形成時のバースト的なSNe IIに伴う銀河風によって、 元素を多く含むガスが銀河から放出された。それは大きなバルク運動エネルギーをもつため、重力ポテンシャルの深い高温銀河団では閉じ込めることができたが、重力ポテンシャルの浅い低温銀河団ほど逃げ出す確率が大きかった。その後、長い年月をかけてSNe Iaが起きるようになった。SNe Iaはバースト的には起こらず、銀河団から逃げ出すほどのバルクエネルギーを持たないため、SNe Ia生成物が徐々にICM中に蓄積されていった。その結果、低温銀河団ほど珪素が鉄に比べて少なく、また星に対する重元素の質量比が減少することにつながったと考えられる。本論文では、低温銀河団で重元素が逃げ出すことが、エネルギー的にも時間的にも可能であることを実際に定量的に示した。数値的に上のシナリオを考えるために、高温銀河団ほどSNe Ia生成物の閉じ込め効率が大きいことを仮定し、理論から予想されるSNe IIとIaの生成物の重元素組成を用いて観測されたICMの重元素組成を再現することで、ICM中の重元素生成におけるSNe IIとIaの寄与の割合を求めた。高温銀河団では鉄はSNe IIとIaの両方から同じくらいの寄与があるのに対し、珪素のほとんどはSNe IIによって生成されていること、低温銀河団では鉄に対するSNe Iaの寄与が70-80%にまで増加していることが確かめられた。いずれの銀河団でもSNe Ia生成物が十分に閉じ込められ、また高温銀河団ではSNe II生成物も完全に閉じ込められていると仮定すると、低温銀河団でのSNe II生成物の閉じ込め効率を計算することができて、温度が下がるにつれて閉じ込め効率は減少し、温度が1keVでは40%以下になることがわかった。 元素を多く含むガスが銀河から放出された。それは大きなバルク運動エネルギーをもつため、重力ポテンシャルの深い高温銀河団では閉じ込めることができたが、重力ポテンシャルの浅い低温銀河団ほど逃げ出す確率が大きかった。その後、長い年月をかけてSNe Iaが起きるようになった。SNe Iaはバースト的には起こらず、銀河団から逃げ出すほどのバルクエネルギーを持たないため、SNe Ia生成物が徐々にICM中に蓄積されていった。その結果、低温銀河団ほど珪素が鉄に比べて少なく、また星に対する重元素の質量比が減少することにつながったと考えられる。本論文では、低温銀河団で重元素が逃げ出すことが、エネルギー的にも時間的にも可能であることを実際に定量的に示した。数値的に上のシナリオを考えるために、高温銀河団ほどSNe Ia生成物の閉じ込め効率が大きいことを仮定し、理論から予想されるSNe IIとIaの生成物の重元素組成を用いて観測されたICMの重元素組成を再現することで、ICM中の重元素生成におけるSNe IIとIaの寄与の割合を求めた。高温銀河団では鉄はSNe IIとIaの両方から同じくらいの寄与があるのに対し、珪素のほとんどはSNe IIによって生成されていること、低温銀河団では鉄に対するSNe Iaの寄与が70-80%にまで増加していることが確かめられた。いずれの銀河団でもSNe Ia生成物が十分に閉じ込められ、また高温銀河団ではSNe II生成物も完全に閉じ込められていると仮定すると、低温銀河団でのSNe II生成物の閉じ込め効率を計算することができて、温度が下がるにつれて閉じ込め効率は減少し、温度が1keVでは40%以下になることがわかった。 最後に、以上の解析では除外してきた銀河団の中心領域でのスペクトルを調べたところ、外側に対してスペクトルが有意に変化しており、平均温度の減少と重元素組成の増加が見られた。2温度プラズマモデルでスペクトルをフィットして重元素組成を求めた結果、cD銀河団ほど鉄の組成比が高いこと、また低温銀河団ほどこの効果が著しいことがわかった。中心での鉄の組成比が温度に対して負の相関を示していることは「ぎんが」衛星で得られた空間平均の鉄の組成比の振るまいとよく似ている。中心でのX線放射率が大きいことを考えると、「ぎんが」の結果は中心での重元素増加の影響を受けていたものと推測される。さて、中心での重元素増加の起源を考察してみると、重元素増加の空間スケールがcD銀河付近であること、cD銀河団だけ重元素増加が見られること、増加に寄与している重元素の量はcD銀河が十分に供給できる量であることから、この重元素増加はcD銀河から放出された重元素を見ているものと考えられる。さらに、珪素と鉄の間の組成比が中心領域で減少してほぼ1になっていることから、cD銀河の放出した重元素についてはSNe Iaの寄与が大きいことが示唆され、楕円銀河で現在はSNe Iaのみ観測されていることと一致する。この結果は、あらためてICM中の重元素に対するSNe Iaの寄与を確認したことになる。  図1:ICM中の珪素と鉄の間の組成比をICMの温度に対してプロットしたもの。単位は太陽組成比。個々の銀河団の統計誤差を小さくするため、同じくらいの温度の銀河団の平均をとったものをプロットしてある。3つのシンボルは、フィットに用いた異なるプラズマモデルの結果に相当する。 図1:ICM中の珪素と鉄の間の組成比をICMの温度に対してプロットしたもの。単位は太陽組成比。個々の銀河団の統計誤差を小さくするため、同じくらいの温度の銀河団の平均をとったものをプロットしてある。3つのシンボルは、フィットに用いた異なるプラズマモデルの結果に相当する。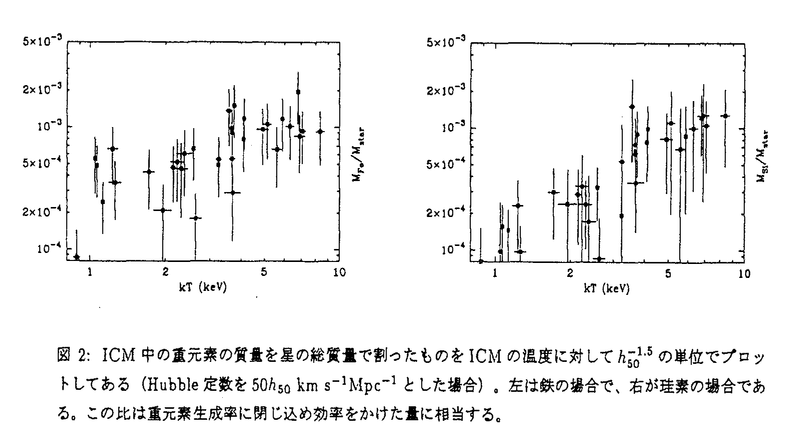 図2:ICM中の重元素の質量を星の総質量で割ったものをICMの温度に対して 図2:ICM中の重元素の質量を星の総質量で割ったものをICMの温度に対して の単位でプロットしてある(Hubble定数を50h50km s-1Mpc-1とした場合)。左は鉄の場合で、右が珪素の場合である。この比は重元素生成率に閉じ込め効率をかけた量に相当する。 の単位でプロットしてある(Hubble定数を50h50km s-1Mpc-1とした場合)。左は鉄の場合で、右が珪素の場合である。この比は重元素生成率に閉じ込め効率をかけた量に相当する。 |