学位論文要旨
| No | 214185 | |
| 著者(漢字) | 井上,公 | |
| 著者(英字) | Inoue,Isao | |
| 著者(カナ) | イノウエ,イサオ | |
| 標題(和) | 電子相関の強い遷移金属酸化物Ca1-xSrxVO3とSr2RuO4の電子状態 | |
| 標題(洋) | Electronic States of Correlated Transition Metal Oxides : Ca1-xSrxVO3 and Sr2RuO4 | |
| 報告番号 | 214185 | |
| 報告番号 | 乙14185 | |
| 学位授与日 | 1999.02.22 | |
| 学位種別 | 論文博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 第14185号 | |
| 研究科 | ||
| 専攻 | ||
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 相関の強い電子系の示す典型的な現象はモット転移である。基本的な金属電子論の説明では金属として振る舞うはずの電子系が、絶縁体になってしまうのである。さらにはこのモット絶縁体と呼ばれる絶縁体にキャリアをドープすることで、驚くべき現象が次々と見つかっている。高温超伝導はまさにその代表例であると言えよう。 固体物理学の歴史を紐解くと、なぜ物質は(バンド)絶縁体になったり金属になったりするのかが正しく理解できたということが、今日の半導体エレクトロニクスの発展を支えているということがわかる。したがって、なぜモット絶縁体になるのかの正しい物理的描像を得ることが、まさに新世代の電子技術への第一歩となることは疑うべくもない。しかしこのような系の基礎的理解は、新しい現象が発見されるたびに揺さぶられ、いまだにコンセンサスを得られていないと言ってもよい。本論文は、そもそもの「モット転移」の物理的描像に対する問題意識を出発点にし、その平均場近似的な描像からは説明し難い興味深い現象について考察することを目的としている。 モット転移は電子どうしに働く強いクーロン反発力(U)が、電子の運動エネルギー(t)に打ち勝つことによって起こる。普通の金属、つまりフェルミーディラック統計によれば、スピンの向きさえ違えば同じ状態を2個の電子が占めてもよいのだが、電子のエネルギーバンド幅(W-2t)が狭い系では、同じ状態を2個の電子が占めたときに生じるUが電子の運動エネルギーの最大値を越えてしまうため、電子はもはや動きまわるよりも、クーロン反発力を避けて各サイトに1個ずつじっとしていた方がよいということなる。これがモット絶縁体である。金属からモット絶縁体への相転移という現象は、多くの電子間に働くクーロン相互作用による多体効果の産物であるから、通常のバンド計算では十分に取り扱うことはできない。こうした多体効果を扱う理論的な試みとしては、無限次元ハバードモデルの動的平均場近似という手法が非常に有効だとされていて、この平均場的描像によると、モット転移の近傍では電子の見掛けの質量(有効質量m*)が発散的に増大するために、電気伝導度がゼロになると言うことになる。ただしこの描像で気にかかるのは、本来は長距離力である電子のクーロン相互作用がほぼ完全に遮蔽を受けて例えば湯川型のような短距離力になってしまっているという前提である。この考え方は通常の金属においては十分に正しい。しかし、一方でクーロン相互作用の遮蔽の効果を通常の金属と同様だと仮定しながら、他方では強い電子相関による電子の局在を考えるというこの描像には疑問が残らないわけではない。このような平均場的描像がどの程度まで正しくて、どういった点で補正を受けなければならないのかを研究する方法については、これまで明確なアイデアがなかった。 そこで我々はぺロブスカイト構造(図1)を有するバナジウム酸化物Ca1-xSrxVO3という物質を考案し、実際にその単結晶を作成することに成功した。この系では伝導のパスに寄与しない(乱れを引き起こさない)Ca2+とSr2+を置換することにより、立方晶のSrVO3から斜方晶のCaVO3へと連続的に構造を変化させることができる。このとき図1に見られるようにVO6八面体が傾くため、Vの3d軌道が作るバンド幅(W)が狭くなって行く。このように系の電子数(3d1)を変えることなく、Wのみを制御することで結果的に系の電子相関の大きさ(U/W)のみを制御することができるわけである。  我々は、Ca1-xSrxVO3のPauli常磁性磁化率、電子比熱係数、電気抵抗率を測定し、有効質量とバンド質量の比m*/mbがxの値に対してどのように変化するかを調べた。ここで、このm*/mbという量はフェルミエネルギー(EF)における状態密度D(EF)(Pauli常磁性磁化率と電子比熱係数にそれぞれ比例する量として実験値から導かれる)と、局所密度近似(LDA)を用いたフルポテンシャルのバンド計算(FLAPW)によって得られる状態密度DLDA(EF)との比で与えられるものである。すなわち である。これは熱的有効質量(thermal effective mass)と呼ばれるものであって、伝導現象などで出てくる有効質量(フェルミ面の各点上で二階微分を取ることによって与えられる有効質量テンソル)とは異なるものである。 本研究によって明らかにされたCa1-xSrxVO3のm*/mbのx依存性は、図2で示す通りである。ここで●がPauli常磁性磁化率から求めたm*/mbであり、■および▲が単結晶および多結晶の電子比熱係数から求めたm*/mbである。●の値を0.5倍したものが○であるが、これが、電子比熱係数から求めた値とほぼ一致している。つまりこの系のWilson比はほぼ2に等しいということがわかる。通常の相関の弱い金属ではWilson比はほぼ1に近い。また強相関の極限でWilson比が2になるということが理論的には議論されており、実際に重い電子系のような非常に強相関の物質系ではWilson比が2になることが実験的に報告されている。さらに、Ca1-xSrxVO3の電気抵抗率の温度依存性をみると、T2に依存する項が室温に至ってもなお支配的である。これは電気抵抗の原因が主に(普通は極低温でしか効いてこない)電子電子散乱であることを意味しており、T2に依存する項の係数Aと電子比熱係数  一方で我々は光電子分光法を用いて系のスペクトル状態密度の変化の様子を探った。論文中では通常の真空紫外光電子分光(UPS)のスペクトルと、入射光のエネルギーを変え、光電子脱出長の運動エネルギー依存性を利用することで表面とバルクのスペクトルの分離を行った全く新しい手法でのバルクスペクトルについてそれぞれ議論しているが、後者が表面の影響を「正しく」除ききれているかということに関しては、現状ではかなり疑問であるため、両方の議論に共通する結論をつかってこの系の電子状態を議論するのが正しい姿勢であろう。ここでは紙面の制約上、後者のみ紹介して、前者にも共通する性質についての議論を行う。 図3に示した光電子スペクトルは、光のエネルギーを変えて測定した一連のデータを光電子の脱出長の運動エネルギー依存性を考慮して解析したものである。この状態密度(1電子励起のスペクトル状態密度。図3下に○で表示)はLDAのバンド計算による状態密度とは大きく異なっており(図3上の太い実線)、この系においては、電子相関が重要であることを示唆している。  そこで、モット転移を記述する非常に有効な手法のひとつである、「無限次元ハバードモデルの動的平均場近似」を用いてスペクトル状態密度を計算してみた。この手法は、多体問題である電子間相互作用を「局所的な不純物と平均場との相互作用を自己無撞着に扱う近似(LISA)」に置き換えるものである。相互作用の自己エネルギー 「バンド幅を広くした」ということは、「「LDAにLISAによる(局所的な)自己エネルギー補正を行った」だけでは不十分な補正を付け加えた」ということに相当している。この原因については、LDAが中途半端に電子相関を扱っていて、とくに自己相互作用の寄与を除ききれてないためであるという考え方もあるが、LDAもLISAも本質的に平均場近似であり、どちらでも十分に扱えていない非局所的な相互作用が大事なのだという考え方もできる。自己エネルギーの本質的な形状を実験的に求めるのは困難(結局は何かの理論と比較しなければならない)なのであるが、ここでは後者の立場から、LDAとU=0のときのLISAの状態密度とのギャップを埋めるために、この未知の相互作用を で表される有効質量において、mk/mb<1となるならば、「 光電子スペクトルとLDAによるバンド計算の結果が大きく異なっているのに、それが有効質量の激しい増大という形で見られないという例は、層状ペロブスカイト構造(図4)を有するルテニウム酸化物Sr2RuO4においても観測された。この物質は高温超伝導物質(La,Sr)2CuO4と同じ構造を持ったCuを含まない物質としては、これまで発見されている唯一の超伝導体(Tc=1.5K)である。この系の伝導特性には大きな異方性があり、擬2次元伝導体とみなすことができる。SrRuO3が強磁性金属であることから、この系でも強磁性的な揺らぎが大きいと考えられているが、実際にその超伝導状態は非常に興味深い特性を示す。比熱やNQRの測定から見積もられるTc以下での大きな残留状態密度や、Tcの不純物および圧力依存性(d Tc/dP<0)が大きいこと、Tc以下で内部自発磁化が出現することなどから、クーパー対はトリプレットでパリティが奇であるp波超伝導であるということが議論されている。  この系のEF近傍の光電子スペクトルを図5に○で示す。細い実線はLDAによるバンド計算にフェルミディラック関数を掛けて実験の分解能を畳み込んだものである。この系の解析では無限次元ハバードモデルは用いず、フェルミ流体論の条件を満たすような現象論的自己エネルギーを導入してフィッティングを行った。我々にとって関心があるのは、特にフェルミレベルでの状態密度であるから、このような解析でも大きな問題はない。それを証明するために2種類の異なる形状の自己エネルギーを導入して計算を行ったが、いずれの場合もフェルミレベル近傍の状態密度を再現することに成功し、そこから見積もられる有効質量の値にも大差はなかった。得られた有効質量の値は比熱から求めた有効質量の値とほぼ一致している。  以上の考察から我々は、モット転移の近傍において状態密度および有効質量は実際にどのように変化するかという問題に対して、以下のような描像を得ることが出来た。系が金属非金属転移の近傍に近づくにつれて、 (1)実際のバンド幅はLDAのバンド幅に比べると広くなり、EFでの状態密度は小さくなる。 さらに、局所的な強い電子相関によって (2)ハバードバンドが出現し、EFには相互作用を繰り込まれた準粒子バンドが残る。 有効質量は で表されるが、ここで、(1)はmk/mbが減少することに相当しており、(2)は このように、LDAの状態密度と光電子スペクトルという非常に大きなエネルギースケールでの計算および実験を比較し、スペクトル強度の高エネルギー側への移動(これが | |
| 審査要旨 | 井上公氏提出の本論文は、主として光電子分光法を用いて、電子相関の強い遷移金属酸化物であるCa1-xSrxVO3とSr2RuO4の電子状態を研究したもので、英文で7章からなる。 遷移金属酸化物のモット絶縁体と金属の間の金属絶縁体転移および、その近傍の金属相は、標準的な金属や金属絶縁体転移に比べて多くの特異な性質を示し、強い電子相関効果が多様な揺らぎや相転移を引き起こしている。このため、近年さまざまな角度から集中的な研究対象となってきた。 電子相関効果に伴う特異性や多様性を系統的に研究するにあたって、光電子分光法は一体の電子のスペクトル強度や状態密度を直接に測定できる手法であるため、電子状態の解明のための欠くことのできない実験手段となってきている。本論文は、上記2種類のペロブスカイト型酸化物の単結晶を作成し、光電子分光実験により、状態密度のエネルギー依存性を詳しく解析している。また、常磁性磁化率、電子比熱係数、電気抵抗率の測定も併せておこなっている。これらの実験解析より、相関の強い金属の特徴のいくつか、特にスペクトル強度のコヒーレント部分とインコヒーレント部分の生じ方や、準粒子の有効質量のふるまい方について、明らかにしている。 第1章では、この論文での考察の背景となる、電子相関の強い系でのモット転移についての理解とペロブスカイト酸化物の特徴をレビューしている。第2章では実験技術の基本的な部分を概説している。第3章から第5章まではCa1-xSrxVO3の電子状態について述べ、第6章はSr2RuO4についておこなわれた研究に充てられている。第7章がまとめである。 まず、第3章から第5章までに述べられているCa1-xSrxVO3の研究では、CaをSrで置換することによって、ペロブスカイト構造のGdFeO3型変形をコントロールし、実効的なバンド幅を変えられることを利用している。このコントロールによって生ずる、相対的な電子相関の強さの変化が、電子状態にどのような影響を与えるのかが重要な着目点である。この点をCa1-xSrxVO3の研究に応用した点は論文提出者独自の着想であり、さらにxを変えていくつもの組成で単結晶試料をはじめて合成し、系統的な研究を推進した点も評価できる。 まずCaVO3についてはほんのわずかな酸素欠損によって磁気抵抗の符号の変化や絶縁体化が生ずることについて詳細な報告がなされ、電子相関効果が大きいことが示唆されている。続いて常磁性磁化率、電子比熱係数、電気抵抗率の測定を行ない、これらの物理量のCa1-xSrxVO3でのx依存性を考察している。有効質量に一定の増大が見られるが、実際にはx依存性はそれほど大きくはない。結果的にはCaとSrの間の置換ではバンド幅の変化もそれほど大きくはなかった。 次に光電子分光による状態密度の測定結果について考察している。光電子分光実験では光の到達できる範囲が試料の表面部分に限られるため、バルクな情報が得られるのかどうかが常に問題となる。論文提出者は、真空紫外光電子分光(UPS)のスペクトルを用いて、入射光のエネルギーを変えて、光電子脱出長の運動エネルギー依存性からバルクのスペクトルを分離する試みを行なった。通常の高分解能光電子分光の測定と併せてこの方法を採用することにより、測定結果の信頼性を評価する努力が行なわれており、この点は評価できる。 得られた状態密度はLDA計算の結果と大きく食い違っており、電子相関効果の重要性を示している。論文提出者は、状態密度を解析する方法として、2つの方法を採っている。一つは動的平均場理論の結果を援用するものであるが、実験結果と動的平均場計算の結果は、単純な比較では全く一致しない。この間のずれを長距離クーロン相互作用に由来する自己エネルギーの波数依存性によって生じたものと解釈して、もとのバンド幅を拡大することによって、実験結果を概ねよくフィットすることができた。もう一つの解析法は、動的平均場の結果を使わずに、より直接的にフィットする方法である。具体的には、コヒーレント部分の強度から自己エネルギーの振動数依存性を決め、フェルミレベル上での状態密度から波数依存性を決める手法である。いずれの場合も振動数依存性から決まる有効質量補正( さらに論文提出者はSr2RuO4についても同様の解析を行ない、有効質量と光電子分光の実験結果から、電子の自己エネルギーの振動数および波数依存性について解析し、実験結果をこれら二つのパラメタでフィットすることに一定程度成功している。 本論文の成果は以下のようにまとめられる。1)光電子分光法を用いて、バンド幅を制御した系で電子相関効果の変化をはじめて系統的に解析したこと、2)この目的のために組成の違う上記一連の化合物の単結晶作成にはじめて成功したこと、3)比熱、帯磁率、電気抵抗の測定も行なって、低エネルギーでの有効質量の系統的な変化を解析し、高エネルギー側での光電子分光の結果と比較検討したこと。これらの3点をあわせた総合的な判断により、バンド幅制御による電子相関の効果の現われ方のいくつかを明らかにし、今後のこの分野の研究の進展に資するところが大きいと判断される。 以上の成果について議論した結果、本論文審査委員会は全員一致で本研究が博士(理学)の学位論文として合格であると判定した。 なお本研究は、東京大学理学系研究科藤森淳助教授ほか27名の研究者との共同研究の部分があるが、上に述べた成果の主要部分について論文提出者が主たる寄与をなしたものであることが認められた。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/50708 |
 はほんのわずかな酸素欠損(
はほんのわずかな酸素欠損( -+0.12 )により低温での磁気抵抗が正から負へと劇的に変化する。さらに同程度にわずかな酸素過剰(
-+0.12 )により低温での磁気抵抗が正から負へと劇的に変化する。さらに同程度にわずかな酸素過剰(
 の間には、やはり重い電子系で報告されている「門脇Woodsの関係」が成り立っている。こうしたことから、Ca1-xSrxVO3の電子相関U/Wは非常に大きいと考えてもよいはずなのだが、m*/mbの値そのものはわずかに1.5程度にとどまっており、SrVO3からCaVO3にかけての変化も非常に小さい。
の間には、やはり重い電子系で報告されている「門脇Woodsの関係」が成り立っている。こうしたことから、Ca1-xSrxVO3の電子相関U/Wは非常に大きいと考えてもよいはずなのだが、m*/mbの値そのものはわずかに1.5程度にとどまっており、SrVO3からCaVO3にかけての変化も非常に小さい。 (k,
(k, )は、したがって、波数kに依存しない局所的なもの
)は、したがって、波数kに依存しない局所的なもの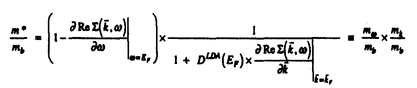
 /mbの増大がmk/mb<1によって押さえられる」ということも可能である。k依存性が、図3のように、バンド幅を広げるように働くならば、mk/mb<1であるから、実際にこのように仮定した自己エネルギーを使ってスペクトルのフィッティングを行ってみた。このとき有効質量が、比熱の測定から導いた(それほど大きくない)有効質量をよく説明することも分かった。
/mbの増大がmk/mb<1によって押さえられる」ということも可能である。k依存性が、図3のように、バンド幅を広げるように働くならば、mk/mb<1であるから、実際にこのように仮定した自己エネルギーを使ってスペクトルのフィッティングを行ってみた。このとき有効質量が、比熱の測定から導いた(それほど大きくない)有効質量をよく説明することも分かった。