(2)頚部浸潤度診断 腫瘍の分化度、組織型、筋層浸潤度に加え、頚部浸潤度も体癌の予後に影響する重要な因子である。FIGOの術後進行期分類ではこれをIIa:頚管腺のみの進展、IIb:頚管間質浸潤、と細分類しているが、fractional curettage、子宮鏡、経膣超音波、CT、MRIといった従来の方法ではIIa期とIIb期を鑑別することは困難である。そこで頚部浸潤度診断における子宮内超音波の有用性について検討した。
本研究に先立ち、頚部病変を認めないvolunteerの32例の婦人(20〜51歳)に対して、informed consentを得たのち経膣超音波法と子宮内超音波法を行い、正常頚部が両走査法にて各々どのように描出されるかを検討し、それに基づき超音波画像による体癌の頚部浸潤度の診断基準を作成した。経膣超音波では32例全例に、頚管腺領域と考えられている舟状の低輝度領域が頚管の周囲に認められた。子宮内超音波ではこの頚管腺領域は周囲の頚部間質領域に比べ19例(59%)で低輝度に、13例(41%)で高輝度に描出されたが、いずれの場合も頚管腺領域のtextureは細かく、間質領域のそれは粗く表示されたため、両領域の鑑別は容易であった。以上の観察をもとに、超音波画像による体癌の頚部浸潤度の診断基準を以下のように作成した。すなわち、体部の腫瘍エコー像に連続して不整なエコー輝度を持つ腫瘍像が頚部に存在する場合、頚部浸潤(+)と診断する。その場合、腫瘍が頚部間質に認められれば頚部間質浸潤(+)、頚管内か頚管腺領域にとどまっていれば頚管腺のみの進展と診断した。
体癌32例(46〜75歳)に対し、術前にinformed consentを得たのち経膣超音波法(5-7.5MHz:モチダ社製ソノビスタ-CS,または-if)と子宮内超音波法を施行し、両走査法により診断した頚部浸潤度と摘出子宮の病理組織学的診断とを比較した。子宮内超音波法が可能であった32例中30例につき検討を行った。経膣超音波では23例(77%)で正診され2例(7%)で過小診断、5例(17%)で過大診断されたが、子宮内超音波では26例(87%)で正診、1例(3%)で過小診断、3例(10%)で過大診断された(表2)。病理組織診にて頚管腺のみの進展であった3例はすべて子宮内超音波で正診されたのに対し、経膣超音波では誤診された。
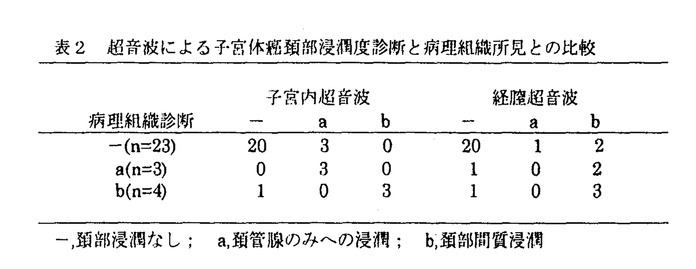 表2 超音波による子宮体癌頚部浸潤度診断と病理組織所見との比較
表2 超音波による子宮体癌頚部浸潤度診断と病理組織所見との比較 子宮内超音波法と経膣超音波法の、頚部間質浸潤の有無についての診断成績を表3に示す。子宮内超音波のspecificityとpositive predictive valueはいずれも100%で、経膣法のそれより高かった。
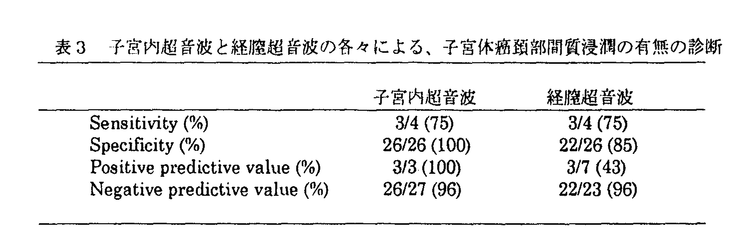 表3 子宮内超音波と経膣超音波の各々による、子宮体癌頚部間質浸潤の有無の診断
表3 子宮内超音波と経膣超音波の各々による、子宮体癌頚部間質浸潤の有無の診断