| 目的 頚椎症性脊髄症は、頚椎の変形や脊柱管狭窄などに起因する慢性脊髄圧迫により発症する。統計的報告によれば、頚椎の変形や脊柱管狭窄は一般成人において数多く認められ、特に高齢者では極めて高頻度に認められる。超高齢化社会を迎えつつあるわが国において、頚椎症性脊髄症の原因となる慢性脊髄圧迫の病態研究は最も重要な研究課題のひとつと考えられるが、その病態、病理、治療などに関して未解決な問題が多い。 急性脊髄圧迫の実験は数多くなされてきたが、これは急性脊髄損傷の研究を目的としている。一方、症状が緩徐に進行する慢性脊髄圧迫モデルの基礎的研究は極めて少ない。ヒトの剖検例、動物実験モデルを使った研究から、慢性脊髄圧迫による脊髄の病理学的変化として、灰白質では神経細胞の脱落および消失が、白質では脱髄などが報告されている。しかし、慢性脊髄圧迫モデルを用いて、その運動機能の変化と病理学的変化を定量的に分析した研究はまだ報告されていない。 本研究の目的は、軽度のあるいは初期の頚椎症性脊髄症に似た経過を再現する慢性脊髄圧迫モデルを小動物で作製し、その運動機能の変化と組織病理学的変化を定量的に分析することにより、頚椎症性脊髄症の病態の一端を明らかにすることである。今回は特に、運動ニューロンの神経細胞死に焦点を当て、定量的分析を行った。 方法 ウイスターラットのC5、C6頚椎椎弓下の硬膜外に、水を吸収することで徐々に膨潤するポリマーシートを挿入し、急性期、慢性期を通じて明らかな神経学的欠損症状を現わさない程度に頚髄が圧迫される状態を作った(圧迫群)。別にコントロールとして、硬膜外に膨潤ポリマーシートを一瞬通すだけで、留置しなかったラットを作製した(シャム群)。ポリマーシートには、ポリウレタンエラストマー自体に水膨潤能力を持たせたエーテル型ポリウレタンを使用した。これはラットの体内で24時間で元の体積の約220%になりプラトーに達する膨潤能を有するものである(図1)。 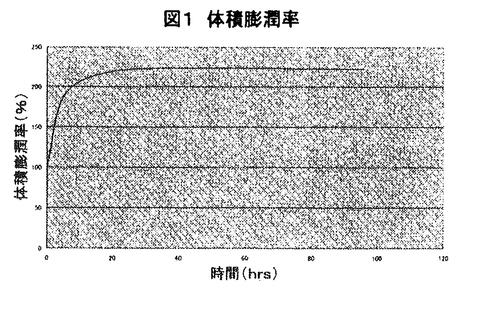 図1 体積膨潤率 図1 体積膨潤率 頚髄圧迫の前後ともに、ラットの自発運動量、強制運動能力を定量的に記録した。具体的には、ラットは実験期間を通じて自由に回転できる回転ケージの中で飼育され、一日に平均何回ケージを回転したかを計算し、自発運動量の指標とした。また、ラットを回転型トレッドミルにのせ、最大何秒間歩行し続けられるかを測定し、強制運動能力の指標とした(ただし、300秒を最大値とした)。 圧迫による頚髄の組織病理学的変化を経時的に観察する目的で、30匹の圧迫群のうち、12匹は手術後25週でsacrificeし(25週圧迫群)、残りの18匹は、各6匹ずつ、1週後(1週圧迫群)、3週後(3週圧迫群)、9週後(9週圧迫群)にsacrificeした。一方、12匹のシャム群は全て手術後25週でsacrificeした。灌流固定後、C5、C6で脊髄の断面積を計測した。C5、C6で上下3,000 mにわたり片側前角にある運動ニューロンの数をカウントし、運動ニューロン密度(/1,000 mにわたり片側前角にある運動ニューロンの数をカウントし、運動ニューロン密度(/1,000 m)を計算した。 m)を計算した。 結果 実験期間を通じて、明らかな脊髄麻痺症状を現わしたラットはなかった。 自発運動量の経時的変化(図2)に関しては、25週シャム群と25週圧迫群の間に有意差は認めなかった(有意水準5%、repeated measure ANOVA)。 強制運動能力の経時的変化(図3)に関しては、25週シャム群と25週圧迫群の間に有意差を認めた(p<0.05、repeated measure ANOVA)。ある週における強制運動能力に関する両群の間の比較では、17週以降有意差を認めた(p<0.05、Mann-Whitney’s U test)。 C5、C6部位の頚髄の断面積は、25週シャム群、25週圧迫群で各々、11.37±0.27mm2、10.09±0.29mm2(平均値±標準誤差)であり、圧迫群はシャム群に比し11.3%の減少が認められた。なお、頚髄の前後径では23%の減少が認められた。 運動ニューロン密度(図4)は、25週シャム群、1週圧迫群、3週圧迫群、9週圧迫群、25週圧迫群で各々、360±10、337±19、332±10、287±16、237±6(平均値±標準誤差)であり、25週シャム群と比較して9週以降有意な低下を認め、圧迫期間が長くなるに従い前角にある運動ニューロンの細胞死が進行する傾向が認められた(p<0.05、Scheffe’s)。一方、白質には明らかな変化を認めなかった。 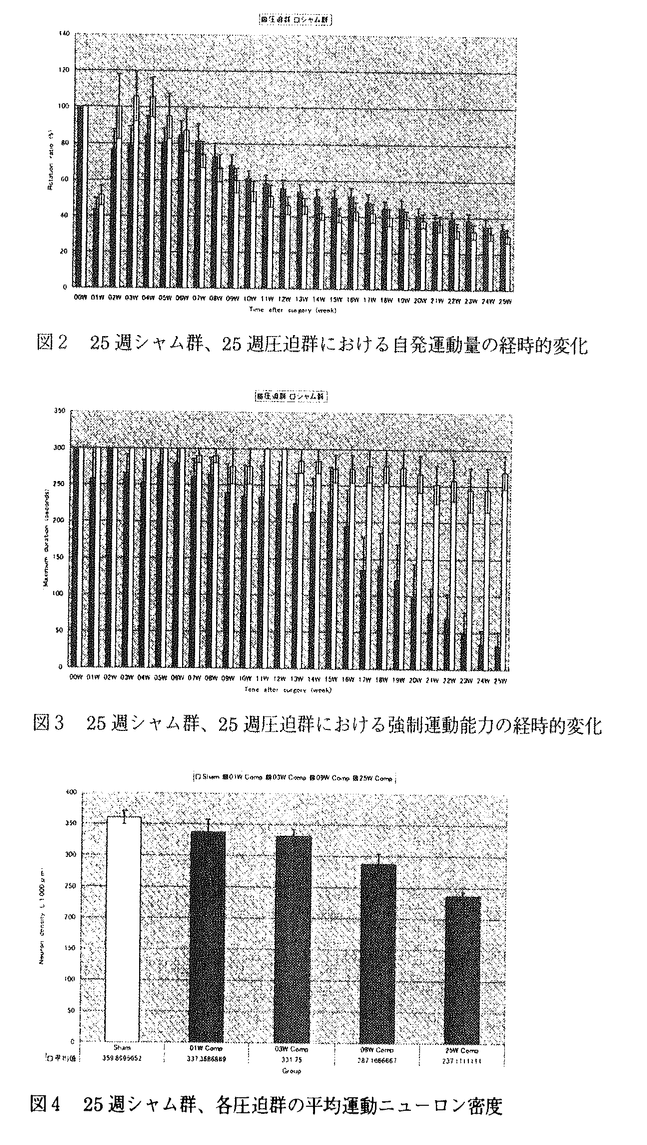 図表図2 25週シャム群、25週圧迫群における自発運動量の経時的変化 / 図3 25週シャム群、25週圧迫群における強制運動能力の経時的変化 / 図4 25週シャム群、各圧迫群の平均運動ニューロン密度考察 図表図2 25週シャム群、25週圧迫群における自発運動量の経時的変化 / 図3 25週シャム群、25週圧迫群における強制運動能力の経時的変化 / 図4 25週シャム群、各圧迫群の平均運動ニューロン密度考察 本研究では、一見明らかな脊髄麻痺症状を示さないながらも、強制運動能力を測定してみると無症候期を経て遅発性に機能障害を現わす慢性脊髄圧迫モデルを小動物で作製することが出来た。従来報告されてきたような漸増性に脊髄圧迫を加えることで脊髄症を現わすモデルと違い、軽度ながら一定の慢性脊髄圧迫により微妙な運動機能障害を現わすモデルと考えられ、軽度の、あるいは初期の頚椎症性脊髄症のモデルになりうると思われる。 慢性脊髄圧迫モデルを使った過去の実験からも、そしてヒトの剖検例を使った研究からも、前角細胞の脱落、消失は報告されているが、本実験において定量的分析からもそれを確認することができた。さらに、脊髄の圧迫期間が長くなるに従い運動ニューロンの細胞死が進行することが示された。断面積にして11.3%という軽度の慢性圧迫でも神経細胞死が起き、しかも進行するということは極めて興味深い結果であると思われる。 脳虚血の研究分野では、弱い虚血負荷により神経細胞の死が極めて緩やかに数日かけて進行する現象が報告されており、これは遅発性神経細胞死delayed neuronal deathとして知られている。本実験では、脊髄圧迫開始から極めて長い時間をかけて進行性に神経細胞死が起きることが示されたが、1週間後では明らかな神経細胞死が認められなかったことからも、初期の脊髄圧迫だけがきっかけとなって起きた神経細胞死とみなすことには無理があると思われる。慢性脊髄圧迫が存在する状況では、伸展、屈曲という頚部の運動により前後から脊髄が絞扼される結果、微小循環のレベルで一過性の虚血が起き、このような一過性の虚血が繰り返されることにより、障害されやすい運動ニューロンが細胞死に至る。本実験で認められた運動ニューロンの死は、このようなメカニズムによる可能性が推測され、このような現象を進行性神経細胞死ongoing neuronal deathと名付けたい。臨床的にも、脊髄圧迫が軽度の場合には、頚椎装具による頚部固定だけで症状が改善することが知られており、このようなメカニズムを支持する事実と思われる。 脳虚血においてみられる遅発性神経細胞死のメカニズムとして、グルタミン酸・カルシウム仮説が提唱されているが、脊髄損傷においても損傷によって二次的に起きる虚血にグルタミン酸が関与している可能性が指摘されている。本実験において認められた運動ニューロンの進行性神経細胞死にグルタミン酸が関与しているかどうかなどは興味のあるところであり、今後の課題である。 頚椎症性脊髄症では、手術により脊髄圧迫を除き、頚椎を固定することでしばしば神経症状が改善する。神経細胞死に陥った運動ニューロンが回復することはないということを考慮すると、慢性脊髄圧迫下で一過性かつ反復性の脊髄虚血のため、電気生理学的機能が障害されているものの細胞死には至っていない神経細胞群があり、それらが頚椎前方除圧固定術により回復する、というメカニズムが示唆される。 将来、本実験モデルを使った研究により、頚椎症性脊髄症の病態がより明らかになり、神経細胞死を減らす薬剤の開発、種々の治療効果の研究などが可能となることが期待される。 |