学位論文要旨
| No | 214537 | |
| 著者(漢字) | 根本,繁 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | ネモト,シゲル | |
| 標題(和) | 海綿静脈洞部硬膜動静脈奇形に対する血管内治療 | |
| 標題(洋) | ||
| 報告番号 | 214537 | |
| 報告番号 | 乙14537 | |
| 学位授与日 | 2000.01.26 | |
| 学位種別 | 論文博士 | |
| 学位種類 | 博士(医学) | |
| 学位記番号 | 第14537号 | |
| 研究科 | ||
| 専攻 | ||
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 内頚動脈、外頚動脈と海綿静脈洞が交通して動静脈短絡が生じた病態は頚動脈海綿静脈洞瘻と呼ばれている。海綿静脈洞には動眼神経、滑車神経、三叉神経、外転神経、内頚動脈が存在し、静脈洞壁には内頚・外頚動脈の硬膜枝が分布し、眼窩、脳表、後頭蓋窩、頭蓋底の静脈との交通があり、海綿静脈洞の病変は多彩な病状を呈すると考えられる。硬膜動静脈奇形は特発性頚動脈海綿静脈洞瘻の原因の一つであり、静脈洞に病変が存在し、海綿静脈洞病変は外科的治療の適応となることは少なく、血管内治療が第一選択とされている。血管内治療の方法として、流入動脈を遮断する経動脈塞栓術、動静脈瘻そのものを静脈側から閉塞する経静脈塞栓術があり、適応、治療法については議論が分かれている。最近では経静脈塞栓術の有効性が報告されているが、本疾患では下錐体静脈洞が閉塞或いは狭窄している症例が多く、海綿静脈洞への到達が困難なことが多い。そこで、閉塞した患側の下錐体静脈洞を通って動静脈瘻のある海綿静脈洞に到達し、経静脈塞栓術を行う方法を開発した。この方法は’クルクル法’として紹介され、良好な成績を挙げている。本研究では海綿静脈洞部硬膜動静脈奇形に対する血管内治療、特にクルクル法を用いた経静脈塞栓術の有効性、問題点について検討を加えた。 1987年から1997年までの11年間に東京大学及びその他の施設において経験した海綿静脈洞部硬膜動静脈奇形74例を対象とした。男性21例女性53例で、年齢は42-81歳、平均62.5歳であった。CTスキャンで眼窩内静脈の拡張を認め、脳血管撮影で海綿静脈洞の硬膜動静脈奇形と診断された。 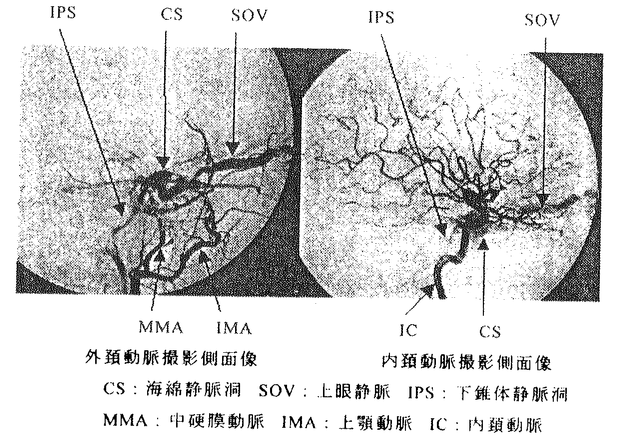 発症後3ヶ月は経過観察し、改善が見られない場合に血管内治療の適応とした。但し視力障害のある症例には可及的早期に治療を行うこととした。治療方法は、経静脈塞栓術を第一選択とし、困難な症例では経動脈塞栓術を行った。血管内治療の方法は以下の通りである。 (1)経動脈塞栓術:右大腿動脈からガイディング・カテーテルを外頚動脈に誘導。マイクロカテーテルを外頚動脈の流入動脈である上行咽頭動脈、中硬膜動脈、副硬膜動脈、上顎動脈、後耳介動脈の各枝に進め、ポリビニル・アルコール・スポンジ粒子を注入し閉塞する。内頚動脈硬膜枝の塞栓術は適応外とする。 (2)経静脈塞栓術:右大腿静脈からガイディング・カテーテルを患測内頚静脈に誘導し、ガイドワイヤーを下錐体静脈洞内に進める。閉塞した下錐体静脈洞ではガイドワイヤーの先進が容易ではないが、ガイドワイヤーをクルクル回転させながら徐々に進めると、閉塞した静脈洞内部を進むことが可能となり、海綿静脈洞へ到達することができる。このガイドワイヤーをクルクル回しながら進める方法は’クルクル法’と呼ばれている。マイクロカテーテルを海綿静脈洞内に誘導し、プラチナコイルを挿入して動静脈瘻を閉塞する。 臨床症状では眼球突出61例(82.4%)、結膜充血59例(79.7%)、複視44例(59.5%)、血管雑音20例(27.0%)、視力障害13例(17.6%)、網膜中心静脈血栓症5例(6.8%)に認められた。血管撮影所見はBarrowの分類では、TypeC2例、TypeD72例であり、殆どがTypeDであった。74例中49例(66.2%)に下錐体静脈洞の閉塞が認められた。 74例中、血管内治療を行ったのは71例であり、3例は自然治癒した(自然治癒率は4%)。治療内容は、経動脈塞栓術のみ13例、経静脈塞栓術のみ52例、経動脈・経静脈塞栓術併用5例、放射線治療(経動脈塞栓術後)1例であった。 治療成績は、経動脈塞栓術を実施した13例中初回治療でシャントが完全閉塞したのは1例もなく、シャント残存11例、変化なし2例であった。結果は治癒9例(69.2%)、改善1例(7.7%)、変化なし1例(7.7%)、悪化2例(15.4%)であった。経静脈塞栓術を実施した52例中、初回治療後のシャント完全閉塞47例(90.4%)、シャント残存5例(9.6%)であった。結果は治癒50例(96.2%)、改善2例(3.8%)であった。治療前に視力低下を伴った13例中、経動脈塞栓術のみを行った3例では、1例は視力の回復が得られず、2例は失明した。これに対して経静脈塞栓術のみを行った9例と経動脈・経静脈塞栓術両方を行った1例では全例発症前の視力に回復した。血管内治療を行った71例全体の治療成績は治癒63例(88.7%)、改善4例(5.6%)、変化なし2例(2.8%)、悪化2例(2.8%)であった。合併症としては、ほぼ全例で術後軽度の頭痛を訴え、嘔気・嘔吐は7例(9.9%)に見られたが、いずれも軽度で数日以内に消失した。一過性の外眼筋麻痺が2例に見られた他には塞栓術手技による重篤な合併症はなかった。 海綿静脈洞の硬膜動静脈奇形は自然治癒する予後良好な疾患であると言われており、軽症例は経過観察し、発症後3ヶ月で改善しなければ治療適応と考えられる。74例中13例(17.6%)に視力障害がみられ、この内5例(68%)に網膜中心静脈血栓症が認められ、失明に至る危険な病態であり、視力低下の見られる症例では、緊急に治療が必要である。 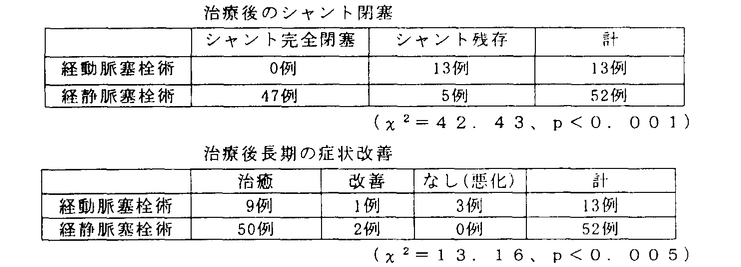 経動脈塞栓術と経静脈塞栓術の治療成績を比較すると、経静脈塞栓術の方がシャントの閉塞では効率が良く( 経静脈塞栓術を行うには、患側の下錐体静脈洞を経由して海綿静脈洞に到達する方法をとるが、到達できなければ反対側の下錐体静脈洞からintercavernous sinusを経由して患側海綿静脈洞に到達するが、何れも技術的に困難な症例が多い。この場合、眼瞼を切開して直接上眼静脈を穿刺してカテーテルを海綿静脈洞へ挿入する方法をとるが、患者の苦痛、穿刺部位からの動脈性出血、術者の放射線被曝線量、上眼静脈閉塞による網膜中心静脈閉塞症、眼瞼切開に伴う眼瞼挙筋損傷による眼瞼下垂などの問題点がある。クルクル法導入により、患側(同側)下錐体静脈洞から動静脈瘻のある海綿静脈洞への到達が可能になり、塞栓術手技が確実に実施できるようになった。クルクル法導入前の29例では16例で下錐体静脈洞から海綿静脈洞への到達が可能であったが(55.2%)、導入後の42例では41例で可能となった(97.6%)。このことから、クルクル法導入により、下錐体静脈洞経由の海綿静脈洞への到達の成功率が有意に向上したといえる( 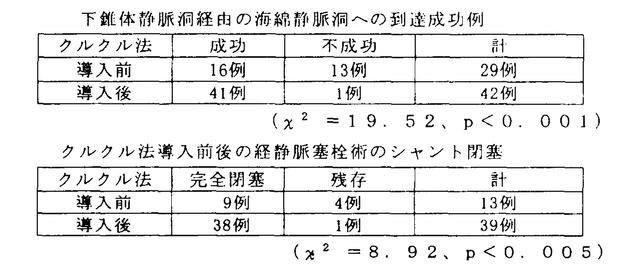 海綿静脈洞部硬膜動静脈奇形の血管内治療では、適応決定には視力障害の有無が重要であり、経動脈塞栓術より経静脈塞栓術の方がシャントの閉塞、治癒効率の点で明らかに優れている。本研究で取り上げたクルクル法により、経静脈塞栓術の技術的な問題点は改善され、本疾患に対する血管内治療の成績は向上した。 | |
| 審査要旨 | 海綿静脈洞部に発生した硬膜動静脈奇形に対する血管内治療では経動脈塞栓術と経静脈塞栓術が行われており、後者の方が前者より有効であると考えられている。しかし後者は技術的に実施困難な症例が多く、治療上の問題点となっていた。本研究はこれに対して経静脈塞栓術に新たな治療手技を導入して治療成績の改善を試みたものであり、以下のような臨床結果を得ている。 1.硬膜動静脈奇形の症例では、正常例に比べて有意に下錐体静脈洞閉塞が合併しており、経大腿静脈、内頚静脈経由での海綿静脈洞への到達が困難である原因であった。 2.閉塞した下錐体静脈洞内をカテーテルを進めるために、ガイドワイヤーで掘り進む手技「クルクル法」を導入した。その結果、海綿静脈洞へのカテーテルの到達が可能となり、経大腿静脈の経静脈塞栓術の成功率が向上した。 3.治療成績は、経静脈塞栓術実施症例では、経動脈塞栓術実施症例に比べると、治療直後の血管撮影上の完全閉塞率が高く、治療早期に症状の改善、治癒が得られ、明らかに経静脈塞栓術の方が治療成績が優れていると結論できた。 4.視力障害を伴う症例では、経動脈塞栓術は無効であり、経静脈塞栓術が有効な治療方法であった。 5.「クルクル法」導入後、本疾患の治療成績が向上したと結論できた。 以上本論文は海綿静脈洞部の硬膜動静脈奇形に対する血管内治療において「クルクル法」という新しい治療手技を導入したことが、治療成績向上に有用であったことを明らかにした。特に視力障害を伴う症例では従来の治療方法では治療困難であったが、本研究で開発した治療方法は、症状改善・回復において臨床的に大きな貢献を果たしたと言え、学位の授与に値するものと考えられる。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/51137 |
 2=42.43、p<0.001)、また治療後早期の治癒(
2=42.43、p<0.001)、また治療後早期の治癒(